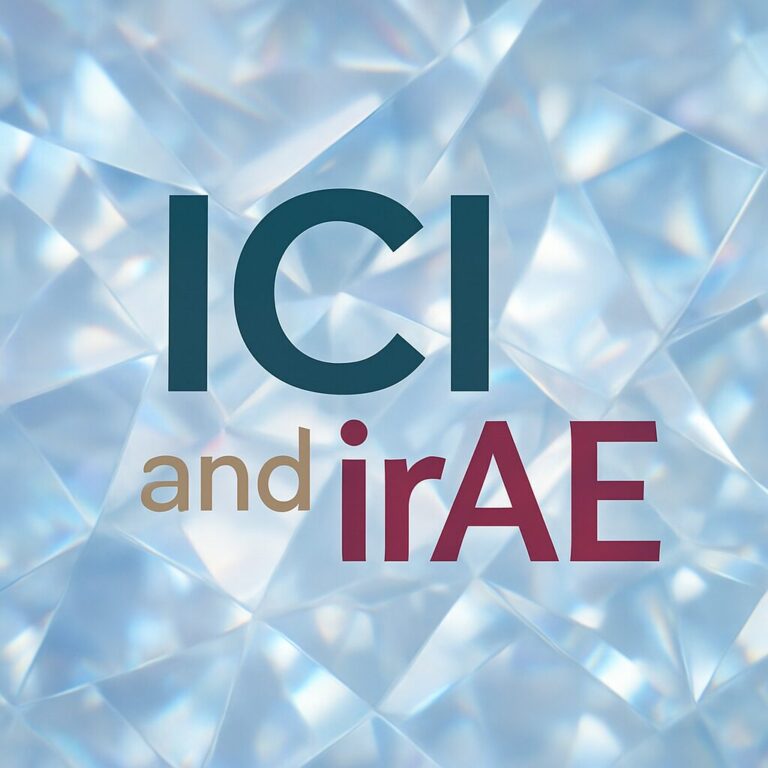医療者全般や最近ICIを使い始めた方向けのおはなしです。
ICI が標準治療に組み込まれた今、irAE(immune‑related adverse events) は避けて通れないテーマですね。
本稿では最新 UpToDate(2025 年 2 月改訂)をもとに、「まずこれだけは押さえる」 という視点で整理しました。
ぜひ日常診療のお供にどうぞ。
ICI の基礎と「irAE」という概念
- 標的分子:PD‑1/PD‑L1(nivolumab〈オプジーボ®〉、pembrolizumab〈キイトルーダ®〉など)と CTLA‑4(ipilimumab〈ヤーボイ®〉等)が主軸。
- irAE の特徴:自己免疫疾患に似た多臓器炎症。
典型例(皮疹・大腸炎・甲状腺機能低下症)だけでなく、非典型・複合パターン にも要注意です。
繰り返します。
典型例ばかりではありません。
「後から振り返るとあれが irAE だったかも……」というケースは少なくありません。 - わからない場合は ICI に慣れた腫瘍内科、臓器別専門医に速やかにコンサルトするのが安全策ですが、使う以上は自分でも初期対応を判断できる知識を持つべき でしょう。
日本で取り扱う主要 ICI(2025 年4 月時点)
| 作用点 | 一般名 | 日本の商品名(保険適用) | 主な適応の一例 |
|---|---|---|---|
| PD‑1 | ニボルマブ | オプジーボ | メラノーマ、非小細胞肺がん(NSCLC)、胃癌ほか |
| ペムブロリズマブ | キイトルーダ | NSCLC、食道癌、大腸癌、尿路上皮癌、腎癌、頭頸部癌、乳癌、子宮体癌、子宮頸癌ほか | |
| セミプリマブ | リブタヨ | 子宮頸癌 | |
| PD‑L1 | アテゾリズマブ | テセントリク | NSCLC、小細胞肺がん(SCLC)、肝細胞癌、胞巣状軟部肉腫 |
| デュルバルマブ | イミフィンジ | NSCLC、SCLC、肝細胞癌、胆道癌、子宮体癌 | |
| アベルマブ | バベンチオ | メルケル細胞癌、腎細胞癌、尿路上皮癌 | |
| CTLA‑4 | イピリムマブ | ヤーボイ | メラノーマ、腎細胞癌、大腸癌、NSCLC、悪性中皮腫、食道癌 |
| トレメリムマブ | イジュド | NSCLC、肝細胞癌(海外併用) |
未承認薬でも治験や適応外使用で遭遇する可能性があるため知識は必須です。
もし抜けがありましたらすみません・・・・
系統別 irAE 一覧
症状・頻度を一目で確認できるようにまとめました。PDF 版を印刷してカルテに挟んでおくと便利です。
| 系統・臓器 | irAE | 症状・所見 | 発症率† |
|---|---|---|---|
| 全身 | 疲労 | 倦怠感 | 16–24% |
| インフュージョン反応 | 発熱・悪寒 | ≤25%(重度<2%) | |
| サイトカイン放出症候群(CRS) | 発熱±多臓器不全 | 稀 | |
| 皮膚 | 発疹・そう痒・水疱症 | 多彩な皮膚症状 | 多い |
| 消化管 | 大腸炎 | 下痢・腹痛 | 多い |
| 肝 | 肝炎 | AST/ALT 上昇 | 多い |
| 肺 | 薬剤性肺障害 (間質性肺疾患と記載) | 咳嗽・呼吸困難感・浸潤影・SpO2低下 | 稀と記載されていますが、 呼吸器内科医は結構遭遇。 |
| 甲状腺 | 低下症 | 倦怠感 | 3.8–13.2% |
| 亢進症 | 動悸 | 0.6–8% | |
| 下垂体 | 下垂体炎 | 頭痛・低Naなど | 0.4–6.4% |
| 副腎 | 不全 | 低血圧 | 0.7% |
| 糖代謝 | 1 型糖尿病 | DKA | 0.2–0.9% |
| 腎 | 急性腎障害 | Cr↑ | 1.5–5% |
| 神経 | ギランバレ 重症筋無力症など | 神経症状 | 4–12% |
| 心 | 心筋炎 | 胸痛・Troponin↑ | ≤1% |
| 血液 | 血小板減少症 | 出血傾向 | ≈1% |
| 自己免疫性貧血 | 貧血 | 稀 | |
| 血球貪食症候群 | 発熱・多臓器不全 | 極稀 | |
| 眼 | ぶどう膜炎 | 視力低下 | <1% |
†頻度は UpToDate に示された最大値・代表値;詳細は原文参照。
とはいえ、この表をご覧いただければお分かりのように、実に多岐にわたる検査項目が含まれており、とてもすべてを覚えきれるものではありません。そして、免疫チェックポイント阻害薬による有害事象は、あらゆる臓器に発症しうることが分かります。
この中でも特に致命的となる可能性がある病態としては、サイトカイン放出症候群(CRS)、薬剤性肺障害、心筋炎などが挙げられます。これらは優先して認識しておくべき重要な合併症です。
また、自覚症状の変化や血液検査の異常値、胸部X線画像の変化、SpO₂を含むバイタルサインのチェックなど、日々の診療のなかで観察可能な所見にも常に注意を払うことが、早期発見・早期対応の鍵となります。
irAE の重症度(CTCAE)と初期対応の原則
| Grade | 定義 | ICI 継続 | ステロイド開始目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽度/無症候 | 可能 | 通常不要・経過観察 |
| 2 | 中等度 | 一時中止 | 0.5 (病態によっては1~2)mg/kg/day(改善≥Grade 1 に) →4 週以上(4~6週?)で漸減 |
| 3–4 | 重度/生命危機 | 原則中止 | 1–2 mg/kg/day(病態によってはステロイドパルスや免疫抑制剤併用) →4 週以上(4~6週?)で漸減 |
irAEに対する治療の主軸は、
- ICIの中止・休薬
- ステロイド(+免疫抑制剤)
です。
内分泌 irAE の一部はホルモン補充だけで再開可能など、臓器ごとに例外があります。
ICI投与前に確認しておきたい検査一覧
ICI治療前には、致命的なirAEを見逃さないための“基準値”を押さえておくことが重要です。
以下の検査項目を「カテゴリー別」に整理しました。
| 📌 カテゴリー | 🧪 具体的な検査項目(例) | 🎯 主な目的・備考 |
|---|---|---|
| バイタルサイン・身体所見 | 血圧、脈拍、体温、SpO₂、体重 | 発熱、ショック、低酸素血症の早期把握に。SpO₂は肺障害の早期発見に重要。 |
| 胸部画像 | 胸部X線、(必要に応じて)胸部CT | 投与前の肺の状態を把握しておくことで、免疫性肺障害の比較・診断に役立ちます。 |
| 血球系 | 赤血球・ヘモグロビン、白血球、血小板、分画 | 感染症やCRS、骨髄抑制のスクリーニング。 |
| 肝機能 | AST、ALT、ALP、γGT、総ビリルビン | ICIによる肝炎・胆管炎の重症度評価に備えます。 |
| 腎・電解質 | クレアチニン、BUN、Na⁺/K⁺、尿検査(蛋白・潜血) | 急性腎障害や電解質異常を早期に把握。尿潜血は腎炎の兆候になることも。 |
| 内分泌機能 | TSH、free T4(±free T3)、コルチゾール、血糖orHbA1c | 甲状腺機能障害、副腎不全、ICI糖尿病などを見逃さないために。 |
| 感染症スクリーニング | HBsAg、HBcAb、HCV抗体、HIV抗原・抗体、T-spot/QFT | 潜在感染症の再活性化リスクを事前に確認。 |
| 心血管系 | 心電図(12誘導)、トロポニンI/T、CK、(必要に応じて)心エコー | ICIによる心筋炎や筋炎の早期発見を目的に。 |
| 凝固・炎症マーカー | PT/INR、APTT、Dダイマー、フィブリノゲン、フェリチン | 血球貪食症候群や播種性血管内凝固などのスクリーニングに。 |
| 肺機能 | スパイロメトリー、DLCO(肺疾患既往例で) | 呼吸機能の評価とICIによる肺障害への備え。 |
💡ポイント
- ✅ SpO₂と胸部X線は、診察のたびに確認してもよい基本項目です
- 🧠 CRS(サイトカイン放出症候群)、心筋炎、薬剤性肺障害は特に致命的になりやすいので、これらに関連する項目は優先してチェックしましょう
- 上記のうち、血算や生化学検査、血糖、凝固検査などは院内のプロトコルに従い、定期的にチェックしてください。
- 📂 「ICI開始前セット」「ICIフォローアップセット」として電子カルテに登録しておくと、漏れなくオーダーできて安心です!

特に呼吸器内科以外の先生方にお願いです。
ICIを導入される前に、ぜひ以下の点をご確認ください。
- 胸部CTおよび胸部レントゲンの撮影
- フォローアップ中の定期的な胸部レントゲン
- SpO₂の測定
これらは決して「呼吸器内科だけの仕事」ではなく、薬剤性肺障害の早期発見と適切な対応において非常に重要なポイントです。
特に、既存の間質性肺疾患(薬剤性でないもの)が背景にあると、ICIによる薬剤性肺障害のリスクが上昇することが知られています。
また、万が一薬剤性肺障害が生じた場合も、治療前後の胸部画像やSpO₂の経時的な変化があることで、
- 発症時期や進行度の評価
- 重症度のグレーディング
- ステロイド治療などの判断
に大きく役立ちます。
レントゲンとSpO₂測定はシンプルかつ低侵襲ですが、薬剤性肺障害の診療には欠かせない“羅針盤”です。
ぜひ、日常診療に組み込んでいただけましたら幸いです。
まとめ
- 前投与検査を必ず行う。
- 投与患者さんの定期チェック:症状スクリーニング+血液検査+SpO2+胸部レントゲン
- 非典型症状を見逃さない:「なんとなくおかしい」に敏感になる。
- 専門家ネットワーク:腫瘍内科・臓器別科・救急と連携し、プロトコルを院内で共有。
結語
irAE は適切に対処すれば治療効果を損ねずに患者さんを守れます。
典型例だけでなく非典型・複合パターンにも目を配り、疑ったら早めに検査・ステロイド・専門家へのコンサルト。
「ICI を扱う者は irAE を制すべし」——このマインドを胸に、明日からの診療に活かしていただければ幸いです。
今回は、ざっくりとおはなししただけですが、今度は別の記事で、いろいろ掘り下げていきたいと思います。
なぜ今回この記事を書いたのか
今回このまとめを作成した理由は、最近 ICI 治療が導入された診療科において、irAE に気づかれず重症化してしまった症例を実際に目にしたことがきっかけです。
呼吸器内科や皮膚科など、比較的早い段階から ICI が導入されており、irAE に関する経験がすでに蓄積されている診療科では、概ね適切なスクリーニングやフォローアップが行われている印象があります。
しかし一方で、最近 ICI が導入された診療科では、irAE に対する初期対応や経過観察が不十分なケースも散見されます。中には、院内で整備されているプロトコルがあるにもかかわらず、その存在が共有されていなかったり、独自の判断で対応がなされてしまった例もありました。
確かに、治療導入直後で手探りになることは避けられない面もあります。ただし、現在では irAE に関する知識や経験が十分に蓄積されており、国内外のガイドラインや施設内のプロトコルも整備されている状況です。その中で、「知らなかった」「見ていなかった」「何となく自己流で対応した」では済まされない段階に来ていると感じています。
irAE は、正しく対応すれば多くが回復可能であり、ICI 治療の恩恵を最大限に引き出すことができます。だからこそ、すべての診療科で「最低限の知識を持ち、迷ったら相談する」文化が根づくよう、情報共有と啓発が必要だと強く思っています。
この記事が、少しでもその一助になれば幸いです。