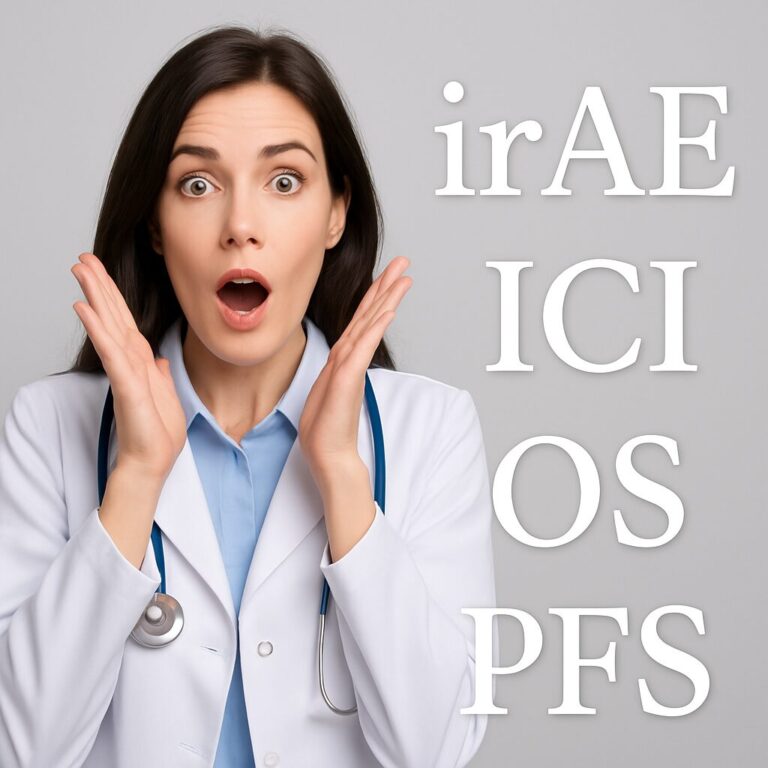Factors Associated with Disease Progression after Discontinuation of Immune Checkpoint Inhibitors for Immune-Related Toxicity in Patients with Advanced Non–Small Cell Lung Cancer. Federica Pecci, Rohit Thummalapalli, Stephanie L. Alden, et al. Clinical Cancer Research 2025.
はじめに

免疫チェックポイント阻害薬(ICI)は、進行非小細胞肺がんの治療に欠かせない存在となっていますね。
ですが、免疫が過剰に反応してしまう「免疫関連有害事象(irAE)」によって、治療を途中で中止しなければならない患者さんも一定数います。

「じゃあ、その後どうなるの?」
「治療をやめたら、すぐにがんが進行してしまうのでは?」
この研究は、irAEによってICIを中止したあとに、病気がどれくらい進行するか?どんな人が長く病気の進行を抑えられるのか?を詳しく調べたものです。
日々の臨床で悩ましい「中止の判断」や「再導入のタイミング」にヒントをくれる内容になっています。
背景と目的
irAEの発症によりICIを中止した進行非小細胞肺癌(NSCLC)患者において、中止後の臨床転帰および病勢進行に関連する因子は、ほとんど明らかになっていない。
方法
irAEによりICI治療を中止した進行NSCLC患者から診療・病理学的データを抽出し、中止後の無増悪生存期間(PFS)および全生存期間(OS)に関連する因子を評価した。
結果
2,794人中10%(271人)がirAEによりICIを中止した。
中止までの治療期間の中央値は5.9か月(範囲:0.03~73.5か月)であった。
中止までの治療期間が長いほど、転帰は良好だった。
ICI治療期間が3か月未満、3~6か月、6か月超の群でのICI中止後の
- PFS中央値はそれぞれ6.2、13.9、25.8か月(P < 0.001)
- OS中央値はそれぞれ21.7、42.7、86.9か月(P < 0.001)
多変量解析では、中止後PFSが長いことと有意に関連したのは、
- PD-L1≧50%、
- 治療によるCRまたはPRの達成、
- 治療期間が3か月超であったこと(3~6か月、6か月超)
であった。
OSが長いことに関連したのは、
- 非扁平上皮癌組織型
- CR/PRの達成、
- および治療期間が6か月超
であったことだった。
irAEの管理目的での免疫抑制薬使用は、中止後の転帰に影響を与えなかった。
結語
irAEによるICI中止後も長期間の病勢コントロールが可能な患者を特定するうえで、治療期間の長さ、CR/PRの達成、PD-L1≧50%、非扁平上皮型組織は重要な予測因子となり得る。

解説しつつ、まとめたいと思います!!
主な結果まとめ|治療期間以上に延びる「その後の時間」
2,794人のうち、約10%(271人)がirAEのためにICIを中止していました。
特に注目すべきは、「治療期間の差」以上に「中止後の生存期間の差」が大きく広がっていたという点です。
| 治療継続期間 | 中止後のPFS中央値 | 中止後のOS中央値 |
|---|---|---|
| 3か月未満 | 6.2か月 | 21.7か月 |
| 3〜6か月 | 13.9か月 | 42.7か月 |
| 6か月超 | 25.8か月 | 86.9か月 |
🟢 ICIを6か月以上継続できた人は、中止後も約2年がんが進行せず、全生存期間は7年を超えていたのです。
この「治療期間(約2倍)の差」が、「生存期間(約4倍)の差」になっているのは驚きですね。
では、どんな人が中止後も治療効果が続いたのか?
📌 良好な中止後予後と関連していた因子:
- PD-L1発現率が50%以上
- 治療で腫瘍が縮小した(CRまたはPR)
- 非扁平上皮がん
- 6か月以上ICIを継続できた
一方、ステロイドや免疫抑制薬の使用の有無は、中止後の生存には明確な影響を与えなかったという結果も、臨床的に安心材料になるかもしれません。
重要な示唆|「6か月以上の治療」でICIの“記憶”が残る?
この研究のもっとも重要なポイントは、
「治療を長くすれば、それだけ中止後も“ICIの効果”が長く残る」ことが示された
という点です。これは、免疫記憶の形成や、腫瘍微小環境の持続的変化によって、治療を中止しても“ICIの余波”が効き続けている可能性を示しています。
実際、著者らは以下のように述べています:
「治療期間とPFS/OSとの関連は非線形であり、9か月を超えると恩恵が頭打ちになる」
つまり、6〜9か月間しっかりICIを使っていれば、その後にirAEで中止しても、がんは長くおとなしくしてくれる可能性が高いのです。
一方で、特に9か月以上でPFS/OSが頭打ちになる(plateauになる)ことからも、「一定期間きちんと治療できた患者では、それ以降のICI継続に大きな追加効果はない」というde-escalationの視点も含意しています。
つまり、 👉 「長く治療できればできるほどいい」ではなく、「6~9か月を超えると、その後の恩恵は限られる」というメッセージも含まれているのですね。
これは「どのタイミングで中止するか?」という臨床判断に、非常に大きなヒントを与えてくれますね。
臨床的インパクト|治療中止後でもあきらめない
この研究は、次のような臨床判断を後押ししてくれます:
- 👉 「irAEでやむを得ずICIをやめるとしても、6か月以上治療できていれば、しばらく再治療せず様子を見る選択もありうる」
- 👉 「逆に、3か月未満での中止は予後が厳しいため、再導入や他治療の検討を早めに行うべき」
また、再導入(rechallenge)のデータも提示されており、ICIを再開した場合でも一定の効果は見込めるが、irAEの再発にも注意が必要です。
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。