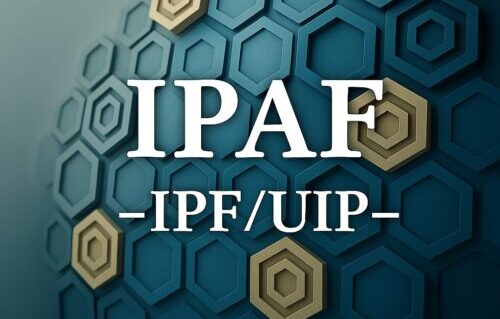タイトルの漢字の画数多いなぁ— 個人的には、IPAFという概念は現在ではやや下火になっていると感じます。
実際、ガイドラインでも「IPAFは研究用の概念であり、実臨床の診断や治療判断には用いるべきでない」と明記されていますね。
そのため、IPAFの考え方は、あくまで研究領域にとどめるべきだと考えます。
ただし、この論文に登場したanterior upper lobeサイン、straightedgeサイン、exuberant honeycombingサインといったCT所見は、覚えておく価値があると感じました。
Evaluation of Autoimmune Features in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Pathologic Usual Interstitial Pneumonia: Implications for CT Patterns and Prognosis. Sohee Park, et al. Radiology, 2025.
はじめに

特発性肺線維症(IPF)は、診断がとても難しい病気ですね。
特に、外科的肺生検で「UIP」(usual interstitial pneumonia)と診断された患者さんでも、CT画像では典型的なUIPパターンにならないことがよくあります。
こうしたCTパターンを、ガイドラインではindeterminate(不定)やalternative diagnosis(他の病気を示唆する)パターンと呼びます。
「じゃあこの人たち、本当にIPFなの?」「何か他の病気(たとえば膠原病)じゃないの?」
そんな疑問が出てきますよね。

このとき注目されるのが、IPAF(interstitial pneumonia with autoimmune features)という考え方です。
ただし注意点として、IPAFは正式な診断名ではなく、まだ研究用の分類です。
最近はこのIPAFという概念もやや下火になり、実臨床でそのまま使うには慎重さが必要と言われています。
今回紹介する論文は、
「病理学的にUIPと診断された患者の中で、自己免疫的な特徴を持つ人はどんな特徴があって、予後に違いがあるのか?」を調べた研究です。
背景
特発性間質性肺炎(IIP)および病理学的通常型間質性肺炎(UIP)を有する患者における、
自己免疫的特徴(IPAF)の臨床的、放射線学的、および予後的意義は十分に評価されていない。
目的
IPF診断のためのCTパターンに応じた自己免疫的特徴を比較し、
IPF-UIP患者におけるIPAFの診断的・予後的意義を評価することである。
方法
本後ろ向き研究では、2013年1月から2020年2月までに外科的肺生検でUIPと診断された患者を対象とした。
臨床的、放射線学的、病理学的な自己免疫的特徴を収集し、現在のガイドラインに基づきIPAFの診断を行った。
さらに、結合組織病(CTD)を示唆するCT所見(anterior upper lobe, straightedge, and exuberant honeycombingサイン)も評価した。
全生存期間(OS)はCox比例ハザードモデルを用いて解析した。
結果
210例(中央値64歳、IQR 60–68歳、男性158例)のうち23例(11.0%)がIPAFに該当した。
CTパターンがindeterminateまたはalternative diagnosisであった患者は、UIPまたはprobable UIPの患者と比較して、
- 病理学的自己免疫的特徴(38% vs 20.3%、P = .005)、
- 血清学的自己免疫的特徴(20% vs 9.8%、P = .04)、
- IPAF(21% vs 4.1%、P < .001)
の頻度が高かった。
しかし、IPAFの診断はOSの予測因子ではなかった(HR 0.81、95%CI 0.38–1.72、P = .58)。
- リンパ濾胞(HR 0.59、P = .02)、
- CTDを示唆するCT所見(HR 0.31、P = .047)、
- 抗線維化薬の使用(HR 0.31、P < .001)
は、いずれも高いOSと独立して関連していた。
一方、CT上の線維化範囲が広いことは、予後不良と関連していた(HR 1.08、P < .001)。
結語
IPF-病理学的UIP患者において、血清学的および病理学的自己免疫的特徴は、indeterminateまたはalternative diagnosisのCTパターンと関連していた。
現在のIPAF基準自体は生存率とは関連しなかったが、一部の病理学的および放射線学的自己免疫的特徴は生存率と関連していた。

勉強してみます!
なにがわかった??
対象はIPFと診断され、外科的肺生検で病理学的にUIPが確認された210人です。
ポイントを簡単にまとめると――
✅ IPAFに該当する患者は11%(23/210人)
✅ CTパターン別では、
- UIPまたはprobable UIPパターンの人よりも、indeterminateまたはalternative diagnosisパターンの人の方が
- 血清検査で自己抗体が出ている割合(20% vs 9.8%)
- 病理でリンパ球浸潤やリンパ濾胞がある割合(38% vs 20.3%)
- IPAFに該当する割合(21% vs 4.1%) が高かったです。
✅ IPAFの有無は生存率には影響しなかった
✅ 代わりに、生存率が良かったのは――
- リンパ濾胞が病理で見られた人(HR 0.59)
- CTでCTD-UIPサインがある人(HR 0.31)
- anterior upper lobeサイン
- straightedgeサイン
- exuberant honeycombingサイン
- 抗線維化薬を使った人(HR 0.31)
✅ CTで線維化が広い人は、予後が悪かった(HR 1.08)
結果をどう考えるか?
この研究が教えてくれることは、とてもシンプルです。
🌟 UIP病理で診断されても、CTパターンが典型的UIPじゃない場合、自己免疫的な要素を持っている可能性がある!
🌟 でも、単純にIPAFに当てはまるかどうかだけでは、患者さんの生存率は予測できない!
🌟 リンパ濾胞や、CTDを示唆するCT所見があるか?が大事!
ここで注意したいのは、
🔵 IPAF診断は正式なガイドラインではないこと。
🔵 自己免疫的特徴があっても、すぐに「膠原病」と決めつけるわけではないこと。
🔵 あくまで「自己免疫の関与があるかもしれないサブグループ」として、注意深く診ていくことが大切ということですね!
つまり、「IPAFですか?違いますか?」ではなく、
「この患者さんにリンパ濾胞はある?」「CTDを示すCT所見はある?」という個別の所見に着目するべき、というわけですね。
改善すべき問題点
もちろん、この研究にも弱点があります。
⚠️ 後ろ向き研究なので、検査や記録にバラツキがあるかも
⚠️ IPAFの基準を少し変更して適用しているので、他の研究と完全には比較できない
⚠️ 実際に膠原病に進展した患者さんはとても少なかった
だから、前向きにしっかり設計された研究が必要だと考えられますね。
臨床的意義
・・・で、私たちが日常診療でこの論文をどう活かすか?ですが、
💡 CTパターンがindeterminateまたはalternative diagnosisだったら、自己免疫的な背景を考える
💡 単純なIPAF診断だけでなく、リンパ濾胞やCTD-UIPサインに注目する
💡 線維化が広い患者では積極的に抗線維化薬を使用し、経過を注意深く見る
これが実践につながるポイントですね!
例えば――
「CTがちょっとtypical UIPとは違うな」「生検でもリンパ濾胞が目立つな」
こんなときには、標準的IPF治療を進めながら、自己免疫疾患への警戒心も持ち続けるという姿勢が大切です!
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。