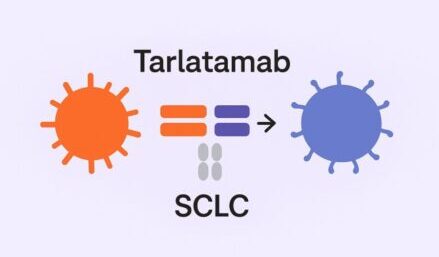「イムデトラⓇ点滴静注用1mg・10mg(一般名:タルラタマブ)」が、2024年12月27日に承認され、2025年4月16日に本邦で発売開始となりました。
今後、小細胞肺癌治療に大きな影響を与える可能性があり、特にサイトカイン放出症候群(CRS)の発生頻度が高いことから、CRSへの注目もますます高まると考えられます。
そこで、今回はこのトピックを振り返ってみました。
はじめに〜小細胞肺癌(SCLC)の厳しい現実〜

小細胞肺癌は「非常に進行が早く、再発もしやすい」タイプの肺がんです。
たとえ初回治療に反応しても、ほとんどの患者さんが数か月以内に再発してしまうのが特徴ですね。
そして2次治療以降になると、
・治療の選択肢がほとんどない
・再び効果が出る確率も低い
・生存期間も短い(多くは8か月以内)
という、非常に厳しい状況が続いていました。
この流れを変えられる新しい治療薬が待ち望まれてきたわけですね。

これまでの小細胞肺癌治療は、細胞障害性抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬(PD-L1阻害薬など)に頼るしかありませんでした。
しかし、小細胞肺癌はMHCクラスIの発現が低いため、免疫系に「がん」と認識されにくいという壁がありました。
そんな中、タルラタマブ(Tarlatamab)は、これまでとは全く異なる新しいアプローチを取っています。
🔵 がん細胞表面に発現するデルタ様リガンド3(DLL3) というタンパク質を標的
🔵 T細胞表面の CD3 にも結合
➡ T細胞とがん細胞を直接引き寄せ、がん細胞を攻撃させる
という、二重特異性T細胞エンゲージャーによる最新の免疫療法なのです!
さらに、DLL3は正常な細胞にはほとんど発現していないため、がん細胞を選択的に狙いやすいという大きなメリットもありますね。
タルラタマブはMHCクラスIに依存せず、T細胞を直接がん細胞へ誘導することで、これまでの免疫逃避メカニズムを乗り越えられると考えられています。
Tarlatamab for Patients with Previously Treated Small-Cell Lung Cancer. Myung-Ju Ahn, Byoung Chul Cho, Enriqueta Felip, Ippokratis Korantzis, Kadoaki Ohashi, Margarita Majem, Oscar Juan-Vidal, et al. The New England Journal of Medicine 2023. 第II相試験(DeLLphi-301試験)
背景
タルラタマブはDLL3とCD3を標的とする二重特異性T細胞エンゲージャー型免疫療法であり、過去にに治療を受けた小細胞肺癌患者において第I相試験で有望な抗腫瘍効果を示した。
方法
本第II相試験では、治療歴のある小細胞肺癌患者に対して、タルラタマブを10 mgまたは100 mgの用量で2週ごとに静脈投与し、抗腫瘍効果と安全性を評価した。
主要評価項目は、盲検独立中央評価による客観的奏効率(完全奏効または部分奏効)とした。
結果
合計220例がタルラタマブを受けた。
患者は中央値2ラインの治療歴を有していた。
腫瘍効果および生存の評価対象患者では、10 mg群の中央値追跡期間は10.6か月、100 mg群では10.3か月であった。
客観的奏効率は10 mg群で40%(97.5%信頼区間29-52%)、100 mg群で32%(97.5%信頼区間21-44%)であった。
奏効を得た患者のうち59%は6か月以上奏効を維持した。
データカットオフ時点で、奏効は10 mg群の55%、100 mg群の57%で持続していた。
無増悪生存期間中央値はそれぞれ4.9か月(95%CI 2.9–6.7)と3.9か月(95%CI 2.6–4.4)であり、9か月時点の全生存率推定値は68%および66%であった。
最も多かった有害事象はサイトカイン放出症候群(CRS)(10 mg群51%、100 mg群61%)、食欲減退(29%、44%)、発熱(35%、33%)であった。
CRSの大部分は第1サイクル中に発生し、ほとんどはグレード1または2であった。
グレード3のCRSは10 mg群で1%、100 mg群で6%に発生した。治療関連有害事象により治療を中止した患者は3%にとどまった。。
結語
10 mg隔週投与のタルラタマブは、治療歴のある小細胞肺癌患者において、持続的な客観的奏効と有望な生存アウトカムを示した。
新たな安全性の懸念は認められなかった。

内容を勉強して感想を述べたいと思います。
結果はどうだったのか?
では、さっそく気になる結果です!
| 項目 | 10 mg群 | 100 mg群 |
|---|---|---|
| 客観的奏効率(ORR) | 40% | 32% |
| 無増悪生存期間中央値 | 4.9か月 | 3.9か月 |
| 9か月時点の全生存率 | 68% | 66% |
| 奏効持続6か月以上 | 59% |
🎯 特に注目なのは、10mg群での奏効率40%!
従来の治療では15%程度だったので、これはかなり大きな飛躍ですね。
しかも、奏効が6か月以上続いた人が半数以上いました。
さらに、9か月経っても約7割の患者さんが生存していたのも心強いですね。
尚、有効性と有害事象とのバランス的には、基本的には10mgベースのレジメンが使われるようになる見込みですね。
実際にイムデトラ(タルラタマブ)の適正使用ガイドにもそのように記載されています。
→イムデトラのホームページリンク
副作用は?
もちろん副作用もありましたが、多くは軽度(グレード1〜2)でした。
✅ よく見られた副作用
- サイトカイン放出症候群(CRS):10 mg群で51%、100 mg群で61%
- 食欲低下
- 発熱
CRSは特に第1サイクル(治療開始初期)に集中していましたが、ほとんどが軽症で、サポート治療(点滴、ステロイド、解熱剤など)でコントロールできました。
ちなみに、グレード3以上のCRSは、10 mg群ではわずか1%のみだったので、10 mgの方が安全性が高そうですね。
今後の課題と注意点
とはいえ、この試験にはまだ課題もあります。
🔵 標準治療との直接比較がされていない(単群試験だった)
🔵 長期生存のデータはまだ成熟していない
🔵 CRSやICANSのリスク管理は引き続き重要
これらを踏まえ、第III相試験が非常に楽しみですね!
臨床的な意義まとめ
タルラタマブは、
・治療歴のある小細胞肺癌患者さんに
・有望な新たな治療選択肢
を提供できる可能性を秘めています。
特に、「もう打つ手がない」と言われた患者さんにも、新たな光が見えてきたのは本当に大きいですね。
肺癌診療ガイドライン2024
肺癌診療ガイドライン2024では以下の推奨があります
CQ18.
全身状態良好(PS 0-1)な再発小細胞肺癌に対してタルラタマブ療法は勧められるか?
推 奨
三次治療以降にタルラタマブ療法を行うよう弱く推奨する。
〔推奨の強さ:2,エビデンスの強さ:C〕
今後、タルラタマブは肺癌診療ガイドライン2024の推奨に基づき、三次治療以降の再発小細胞肺癌において実臨床で使用されていくと考えられます。
有効性に加え、CRSなど特有の有害事象への理解と対策が、より一層重要になっていきますね。
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。