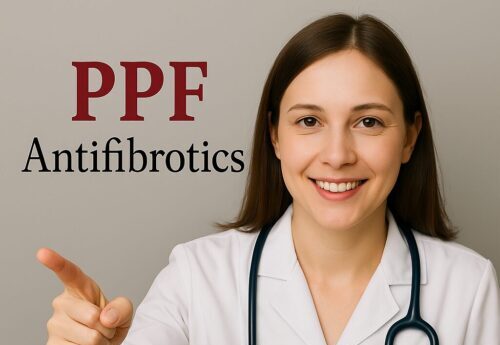ただし一部の患者は治療後も進行。
今後はそういった症例にネランドミラストなど新薬の活用にも注目ですね。今回の論文の主旨とは異なりますが・・
Lung Function Course of Patients With Pulmonary Fibrosis After Initiation of Anti‐Fibrotic Treatment: Real‐World Data From the Dutch National Registry. Mark G. J. P. Platenburg, Gizal Nakshbandi, et al. Respirology 2025.
はじめに

肺線維症という疾患は、肺の実質が線維化し、徐々に肺機能が失われていく病気です。
中でも「特発性肺線維症(IPF)」は代表的な進行性疾患として知られていますね。
最近では、IPF以外の疾患でも同様の進行パターンを示すものがあり、「進行性肺線維症(PPF)」というカテゴリーが提唱されています。
PPFに関する関連記事「PPFとPF-ILDって何が違うのか?わかりにくいですね。」は<こちら>

抗線維化薬(例えばニンテダニブやピルフェニドン)は、IPFでの有効性が確立されており、PPFに対しても有望とされています。
ただし、PPFに関してはリアルワールドデータが少なく、実際の臨床でどれくらい効果があるのかは十分に分かっていませんでした。
そこで本研究では、オランダ全国のレジストリデータを用いて、抗線維化薬開始前後の肺機能(FVCとDLCO)の推移を評価したというわけです。
背景
PPF患者における抗線維化薬治療後の肺機能経過に関する実臨床データは限られている。
我々は、抗線維化治療を開始したPPFおよびIPF患者における努力性肺活量(FVC)の低下を評価した。
方法
オランダ全国16病院を対象とした多施設レジストリ研究である。
抗線維化薬による治療を受け、治療前後に少なくとも2回の肺機能検査を受けた患者を対象とした。
抗線維化治療の開始を基準点とし、その前後1年間の肺機能の推移を線形混合効果モデルにより解析した。
結果
計538名(PPF: 142名、IPF: 396名)のデータを解析した。
PPF群では、抗線維化治療開始前の年間FVC平均低下量は412 mL(95% CI: 308–517 mL)であったが、治療後は18 mL(95% CI: 9–124 mL)と大幅に減少した。
IPF群では、それぞれ158 mL(95% CI: 78–239 mL)、38 mL(95% CI: 24–101 mL)であった。
両群ともに治療後のFVC低下が有意に抑制されたが、その変化はPPF群の方が顕著であった(p = 0.0006)。
治療開始から1年以内に、PPFの23.9%、IPFの28.0%の患者が病勢進行を示した。。
結語
IPFおよびPPFのいずれにおいても、抗線維化治療の開始によりFVCの低下は有意に緩やかになった。
しかしながら、依然として多くの患者が病勢進行を示しており、こうした患者の早期同定と治療戦略の最適化が求められる。

勉強したいと思います!!
どういう結果だったの?
| 疾患 | 抗線維化薬 開始前 | 抗線維化薬 開始後 | 幅 |
|---|---|---|---|
| PPF | 年間 -412 mL | 年間 -18 mL | 約+394 mL |
| IPF | 年間 -158 mL | 年間 -38 mL | 約+120 mL |
つまり、抗線維化薬を使うと、肺活量の減り方がぐっと緩やかになった、ということですね。
さらに、治療後1年で約24%のPPF患者と28%のIPF患者が病勢進行を示しました。治療がうまくいかない人も一定数いることがわかります。
抗線維化薬を使うことで、IPFだけでなくPPFの患者さんでも肺活量の減少スピードがはっきりと抑えられた、というのは大きな発見です。
ただ、PPFの患者さんでは、抗線維化薬を使い始めるまでに時間がかかっていた(診断から治療まで約400日)という点は見逃せません。
一方でIPFでは、すぐに治療開始されていました(約35日)。
これは、「PPFは初めは免疫抑制薬だけで治療する」ことが多いからですね。
また、約4人に1人は治療後も進行していました。このような「効かない患者さん」を早めに見つけて、新しい薬や治験に進める必要があります。
改善すべき問題点
- この研究は「観察研究」であり、治療効果の厳密な証明(因果関係)はできません。
- PPFのなかでもCTD-ILDやfHPなど個別の疾患群での違いは解析されていません。
- 症状や画像による進行の判断は含まれておらず、進行の定義が肺機能の変化だけに限られています。
あと重要な点。
この研究、抗線維化薬の効果はしっかり見てるんですが、ニンテダニブとピルフェニドンの違いは解析されていません。
PPFでは約9割がニンテダニブ、IPFでも6割弱がニンテダニブでしたが、肺機能の推移(FVCやDLCO)は両薬剤まとめて解析されています。
つまり、「抗線維化薬=効いてる」はわかるけど、どっちの薬がより効いてるのかは不明。
ここ、ちょっとイケてないポイントですね。サブ解析が欲しかったところです。
臨床にどう活かす?
この研究結果は、PPFでも抗線維化薬を早めに使うことが有効であることを示しています。
具体的には:
- 「膠原病で徐々に肺が硬くなってきた患者さんに、免疫抑制薬だけで様子を見ている状況」で、
- FVCが落ちてきたら早期にニンテダニブ導入を検討すべきという判断材料になります。
さらに、治療後も進行する患者さんについては、早期からモニタリングして治験などへ導入する体制が重要になってきます。
もしかすると、最近ベーリンガー社の公式サイトで紹介されたネランドミラストが承認されれば、今後このような症例に対する新たな治療薬の選択肢になるかもしれませんね。
PPFに関する関連記事「PPFとPF-ILDって何が違うのか?わかりにくいですね。」は<こちら>
関連記事「ベーリンガー・インゲルハイム社のネランドミラストが、IPFに引き続き、PF-ILDでも第三相試験でFVC低下を抑制したそうです。」は<こちら>
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。