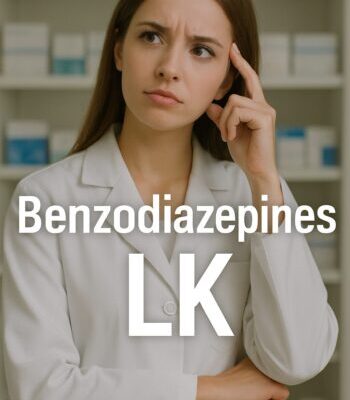Léa Montégut et al. Benzodiazepines interfere with the efficacy of pembrolizumab-based cancer immunotherapy. Results of a nationwide cohort study including over 50,000 participants with advanced lung cancer. OncoImmunology 2025.
はじめに

がん免疫療法の進歩により、非小細胞肺がん(NSCLC)に対する治療選択肢は大きく広がりましたね。
特にPD-1阻害薬であるペムブロリズマブは、PD-L1発現に応じて単剤あるいは化学療法との併用で使用され、標準治療の一角を占めています。
ただし、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の効果は患者間で大きく異なり、その背景には併用薬、腸内細菌叢、全身状態などが複雑に関与しています。

この研究では、ベンゾジアゼピン系薬剤(BZD)が免疫療法の効果を低下させるのではないかという仮説を、フランスの大規模コホートを用いて検証しています。
これは、抗生物質やPPIといった薬剤が免疫療法に影響するという先行研究と同様の視点に立った、臨床的に非常に重要な問いですね。
背景
我々は以前、ジアゼパム結合阻害因子(DBI、別名エンドゼピン)が、GABA-A受容体に作用する内因性ベンゾジアゼピンとして機能し、非小細胞肺がん(NSCLC)の診断リスク因子となる可能性を報告した。DBIの抗体中和は、免疫療法の有無にかかわらず、前臨床モデルにおいてNSCLCの免疫監視を改善した。
フランス・カナダの小規模コホート(n=205)でのパイロット研究では、PD-1/PD-L1阻害薬を投与されたNSCLC患者において、ベンゾジアゼピン(BZD)使用が無増悪生存期間(PFS)の短縮と関連していた。
方法
本研究では、ペムブロリズマブ治療を受けた進行NSCLC患者を対象としたフランス全国規模の後ろ向き解析を報告する。
結果
療開始後2か月以上生存した患者(n=31,479)のうち、37.7%(n=11,878)は治療開始の90日前から30日後の間にBZDを2回以上処方されていた。
BZD非使用者(n=19,601)と比較して、BZD使用者では全生存期間(OS)が有意に短縮していた(ハザード比=1.08、95%CI: 1.04–1.12、p<0.001)。
この影響は、年齢、性別、併存疾患、治療戦略、他の併用薬などの要因を補正するIPTW法によっても持続した。
ONCOBIOTICS研究のサブセット(n=556)において、BZD使用は腸内細菌叢の異常(ディスバイオーシス)および免疫療法の予後不良と関連するTOPOSCOREの悪化とも関連していた。
結語
本研究は、BZD使用がペムブロリズマブを受けるNSCLC患者の独立した予後不良因子となりうることを示しており、今後はBZDの中止またはDBI中和による免疫療法応答改善の可能性を検討すべきである。

勉強したいと思います!!
どんな結果だったか?
対象と方法:
- 対象者数:ペムブロリズマブ初回治療を受けた進行NSCLC患者 31,479人
- BZD使用者:治療開始90日前~30日後に2回以上の処方があった者=11,878人(37.7%)
- 非使用者:19,601人
主要アウトカム:
- 全生存期間(OS)
- BZD使用者は非使用者に比べて有意に短命(HR=1.08、95%CI: 1.04–1.12、p<0.001)
- IPTW(逆確率重み付け)により、多変量補正後もこの結果は有意
腸内細菌との関連(ONCOBIOTICSサブ解析):
- BZD使用者は腸内の有害細菌群(SIG1)優位となる傾向あり
- 特にTOPOSCORE(細菌叢バランスの指標)が悪化
- BZD+抗菌薬の併用でより有意にOSが低下
この研究から何が読み取れる?
この研究は、ベンゾジアゼピンの使用がペムブロリズマブを用いた免疫療法の効果を低下させる可能性を示唆していますね。
著者らは、BZDが直接的に免疫抑制的に働く可能性の他に、腸内環境(腸内細菌叢)を介して間接的に免疫応答を抑える機序を提示しています。実際に、BZD使用者では腸内の「悪玉菌」が増えており、抗腫瘍免疫を抑制する方向に傾いていたと可能性が挙げられるかもしれません。
ただし、この研究は観察研究であるため、「因果関係の証明」にはさらなる前向き研究や介入研究が必要ですね。
限界と注意点
- この研究では、BZD使用が免疫療法中の予後に悪影響を及ぼす「関連」が確認されました。しかし、重要な点として、これは後ろ向き観察研究であり、因果関係は証明できません。交絡の可能性をいくら統計的に補正しても、「不安・不眠・緩和ケア」など、BZDを処方される背景を完全には補正できない点が限界なのです。
- 腸内細菌叢の変化が免疫応答を抑制している可能性もありますが、これも因果関係の証明には至っていません。「BZDが腸内環境を乱す」あるいは「腸内環境が悪いからBZDが必要になる」のどちらかは現時点では断定できません。
- がんの分子プロファイル(PD-L1発現、腫瘍変異負荷など)がデータベースには存在しないため、免疫療法の効果を左右する本質的な因子を考慮できていません。
- 使用量・使用期間の検討がなされていないため、用量依存性が評価できていないのも課題です。
実臨床にどう活かす?
- この研究結果は、がん患者に対してBZDを処方する際には慎重な判断が求められるという重要なメッセージを示していますね。
- たとえば、不安や睡眠障害に対してBZDが習慣的に処方されがちですが、免疫療法中の患者には非ベンゾ系の薬剤(例えばSSRIや非薬物療法)への切り替えを検討すべきかもしれません。
- 緩和ケアや精神科との連携をより慎重に行う必要があるかもしれません。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。