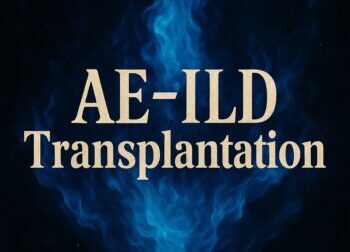海外では、間質性肺疾患(ILD)や間質性肺炎の急性増悪(AE)に対して、緊急の肺移植が実施されるケースがあるそうです。
一方で、日本では現時点ではこのような対応は難しく、制度やドナー数、医療体制など複数の課題が横たわっています。
それでも、将来的にAEに対する肺移植をどう位置づけていくべきかは、今後ぜひ議論を深めたい重要なテーマです。
Lei Yang, et al. Prognosis of Lung Transplantation in Patients with Acute Exacerbations of Interstitial Lung Disease: A Meta-Analysis Based on Cohort Studies. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2024.
はじめに

間質性肺疾患(ILD)は慢性進行性の肺の病気ですが、ある日突然、「急性増悪(AE)」を起こすことがあります。この急性増悪を起こすと、予後は一気に悪化します。
とくにAE-IPF(特発性肺線維症の急性増悪)は、入院死亡率が50~60%に達するとも言われています。
この論文は、中国・アメリカ・韓国などで行われた肺移植成績のデータをまとめ、急性増悪中のILD患者に肺移植を行っても予後は悪くならないという結果を出したものです。

日本では臓器提供数が非常に少なく、肺移植の年間数は100件未満で、そのうちAE-ILDでの緊急登録・移植の実状はわかりません。
米国では緊急度(LASスコア)に応じて迅速に移植が行われるため、AE発症から短期間で移植が実現している点が大きな違いです。
背景
このメタアナリシスは、急性増悪を呈した間質性肺疾患(AE-ILD)患者に対する肺移植の予後を、安定期の間質性肺疾患(stable ILD)患者と比較して検討することを目的とした。
方法
PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane Libraryにて詳細な文献検索を行い、主要アウトカムとして全生存率(OS)、急性細胞性拒絶反応(ACR)、初期移植肺機能不全(PGD)、および入院期間(LOS)を設定した。
結果
本メタアナリシスには5件のコホート研究が含まれ、AE-ILD群には183例、stable ILD群には337例が登録された。
周術期アウトカムに関して、
- ACR(RR = 0.34, p = 0.44)および
- PGD III(RR = 0.53, p = 0.43)の発生率に群間差は認められなかったが、
- LOSはAE-ILD群で有意に延長していた(平均差 = 9.15日, p = 0.02)。
また、
- 90日OS(RR = 0.97, p = 0.59)、
- 1年OS(RR = 1.05, p = 0.66)、
- 3年OS(RR = 0.91, p = 0.76)
においても有意差は認められなかった。
結語
AE-ILD患者に対する肺移植は、stable ILD患者と比較して劣らない有効性を示しており、AE-ILDに対しても肺移植は有望な治療選択肢の一つである。

勉強したいと思います!!
なにがわかったか?
この研究では、AE-ILD患者(183人)と安定期ILD患者(337人)を比較しました。
✅ 周術期の合併症
- 急性細胞性拒絶反応(ACR):AE群と差なし(p=0.44)
- 初期移植肺機能不全(PGD):AE群と差なし(p=0.43)
- 入院期間(LOS):AE群で9日ほど長い(p=0.02)
✅ 生存率
| 生存率 | 差 |
|---|---|
| 90日後 | 差なし(RR=0.97) |
| 1年後 | 差なし(RR=1.05) |
| 3年後 | 差なし(RR=0.91) |
👆つまり、AEでも肺移植さえ受けられれば、生存率は落ちないということですね。
🟨 日本との違い:
日本では、AE-IPFにより人工呼吸器管理を要する重症患者が肺移植に至るケースは非常に稀であり、実際に移植に至った症例がどの程度存在するかも明らかではありません。
呼吸不全に陥った段階で、一般的には「移植不適」と判断されることが多いのが現状です。
一方、米国や韓国では、ECMOや人工呼吸器管理下での緊急肺移植が一定数実施されており、こうした急性期移植のシステムが運用されています。
つまりどういうことか?
この研究の臨床的意義は明確です。「AEだから移植できない」とは言い切れないという強いメッセージです。
日本では「AEで呼吸器管理下=移植不適」とされがちですが、このデータを提示することで移植適応の再考・国レベルでの政策提言につながる可能性があるかもしれませんね。
今日からの診療にどう活かす?
日本では、肺移植の待機期間が長く、登録から実施までに約900日を要するとされています。
そのため、安定期に移植登録を行っても、待機中に急激に病状が悪化し、移植に至らずに死亡してしまうケースが少なくありません。
このような背景から、AEの状態で即座に移植を行うという運用は、現状の日本の医療体制では現実的には困難です。
とはいえ、ドナー数の増加や提供体制の整備、急激に悪化した患者に対して迅速かつ適切に移植適応を判断・優先できるようなシステムの構築が進めば、この課題は将来的に解決し得ると考えられます。
現時点では、こうした対応が私たちの日常診療にすぐに反映されるわけではありませんが、将来に向けて議論を深めていくべき重要なテーマであることは間違いありません。
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。