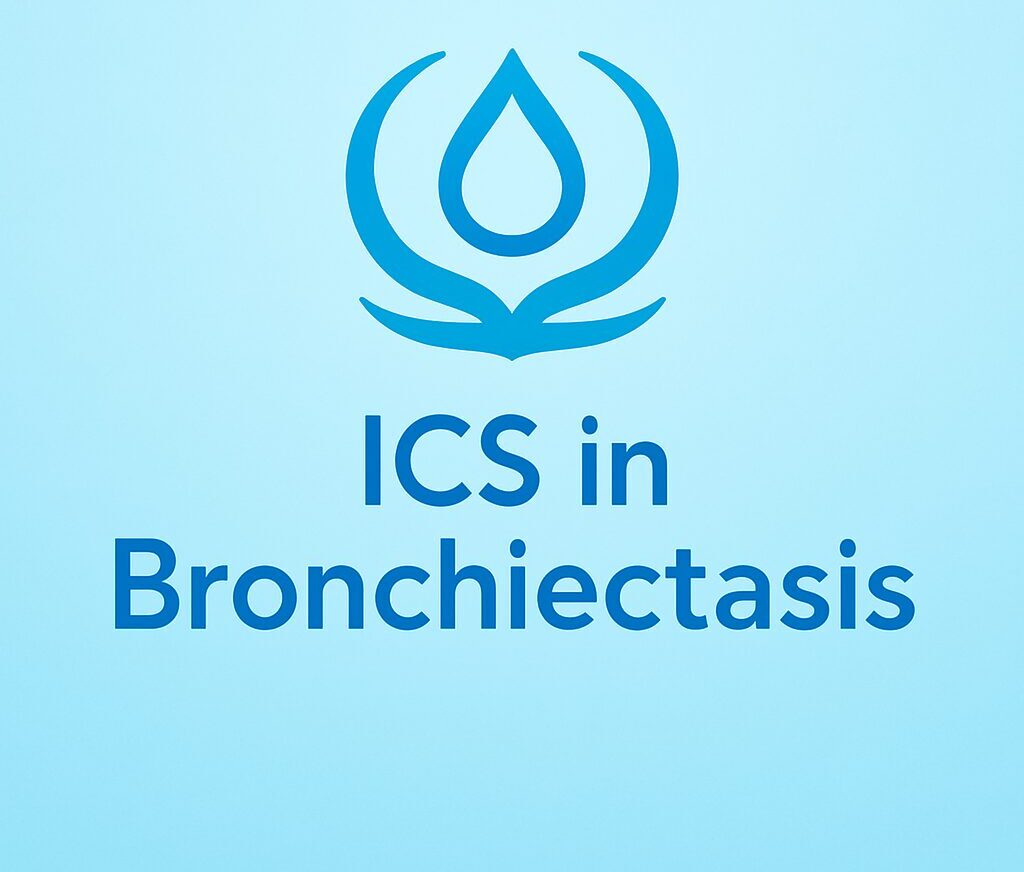Use of inhaled corticosteroids in bronchiectasis: data from the European Bronchiectasis Registry (EMBARC). Jennifer Pollock, Eva Polverino, Raja Dhar, et al. Thorax 2025.
はじめに

吸入ステロイド(ICS)は、炎症を抑える強力な薬剤であり、喘息や好酸球性COPDにおいては有効性が証明されています。
しかし、気管支拡張症の炎症は主に好中球性であることが多く、ICSの効果は限定的とされています。
そのため、欧州呼吸器学会などのガイドラインでは、ICSは喘息やCOPD、ABPAを合併する場合にのみ推奨されています。

それにもかかわらず、実臨床ではICSが広く使用されており、なかにはガイドラインで適応がない患者にも使用されているケースが見られます。
本研究では、ヨーロッパ31カ国からのデータを用いて、ICSの使用実態とその臨床的特徴、長期転帰との関連を解析しました。

背景
現在の気管支拡張症ガイドラインでは、喘息、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)を合併する患者を除き、吸入ステロイド(ICS)の使用は推奨されていない。
本研究では、ヨーロッパにおける気管支拡張症患者に対するICSの使用実態を明らかにすることを目的とした。
方法
本研究は2015年から2022年にEMBARCに登録された気管支拡張症患者を対象とした。
登録時点でのICS使用の有無により群分けし、ICS使用と関連する臨床的特徴を検討した。
最長5年間にわたり、増悪、入院、死亡といった臨床転帰を追跡した。
さらに、血中好酸球数が上限基準値を超えているかどうかにより、ICS使用の増悪抑制効果が変化するかを検討した。
結果
解析対象は19,324例であり、そのうち10,109例(52.3%)が登録時点でICSを処方されていた。
喘息、COPD、ABPAの既往を除外した9,715例のうち3,174例(32.7%)がICSを使用していた。
ICS使用率は国によって17%から85%と大きく異なっていた。
ICS使用群は非使用群に比べて病態が重く、肺機能低下、Bronchiectasis Severity Index(BSI)のスコア上昇、増悪頻度の高さがみられた(p<0.0001)。
全体ではICS使用により増悪や入院のリスクは低下しなかったが、血中好酸球数が高値のサブグループでは、増悪頻度の有意な減少が認められた(相対リスク0.70、95%CI: 0.59–0.84、p<0.001)。
結語
気管支拡張症におけるICSの使用は広く行われており、ガイドラインで推奨されない症例にも使用されている。
血中好酸球数が上昇している患者では、ICSにより増悪頻度が減少する可能性がある。
🫁 気管支拡張症と吸入ステロイド:ガイドラインと現場のギャップを埋める知見
🔰 そもそも「気管支拡張症」とは?
気管支拡張症(bronchiectasis)は、気道(気管支)が異常に拡張し、慢性的な膿性痰や感染、反復する増悪を伴う疾患です。炎症の主体は多くの場合、好中球です。
🧪 ICSを使っていいのか?
ICSは、喘息や好酸球優位のCOPDにおいて抗炎症薬として有効ですが、気管支拡張症における効果は限定的とされています。
その理由は、
- 気管支拡張症では好中球性炎症が主体 → ステロイドが効きにくい
- ICSにより肺感染症(特にNTMやP. aeruginosaなど)が増える懸念がある
という背景があるためです。
📌 ガイドライン(ERS/BTS)では以下のように記載されています:
ICSは以下の合併がある場合に限定して使用を推奨
- 喘息
- ABPA(アレルギー性気管支肺アスペルギルス症)
- COPD(特に好酸球高値、増悪型)
💡 結果のポイント
ICSは予想以上に使われている!
- 全体の52.3%(約1万人)がICS使用
- 喘息・ABPA・COPDの既往がない「適応外患者」にも32.7%がICSを処方されていた
→ ガイドラインでは非推奨ですが、現場では重症例に使われている実態が明らかになりました。
ICS使用者と非使用者の間で、気管支拡張症の既知の原因や併存疾患の頻度は概ね類似していましたが、以下のような差異が観察されました:
- 原発性線毛運動障害症(PCD):ICS使用者でより頻度が高かった(5.6% vs 3.0%)
- 結核(TB):ICS使用者でより頻度が高かった(11.4% vs 9.5%)
- 骨粗鬆症:ICS使用者で有意に高頻度(11.5% vs 9.9%、p=0.016)
- 副鼻腔炎:ICS使用者で有意に高頻度(21.2% vs 16.6%、p<0.001)
- 鼻ポリープ:ICS使用者で有意に高頻度(6.2% vs 4.0%、p<0.001)
一方で、肝疾患(0.3% vs 0.7%、p=0.030)および悪性腫瘍(8.6% vs 10.4%、p=0.005)の併存頻度はICS使用者の方が有意に低い結果となりました。
ICS使用者はより重症
- BSI(Bronchiectasis Severity Index)スコアが高い
- FEV1低下、喀痰量増加、増悪頻度↑、入院歴↑
- 抗菌薬やマクロライド、吸入抗菌薬の使用率も高い
→ “とにかく重症だからICSを使っている”傾向があります(=指示バイアスの可能性)。
ICS使用者は感染リスクが高い?
- P. aeruginosa, H. influenzae, S. pneumoniae の分離率が非使用群より高い
- ただしNTM感染の頻度は逆に低い
→ ステロイドの免疫抑制作用により、細菌定着や感染リスクが増す可能性?
全体としてはICSは有害?
ICSが推奨されていない気管支拡張症患者における結果
- 増悪頻度:
- 未調整:IRR 1.31(95% CI 1.21–1.43、p<0.001)
- 調整後:IRR 1.19(95% CI 1.10–1.30、p<0.001)→有意に高い
- 入院頻度:
- 未調整:IRR 1.24(95% CI 1.09–1.42、p=0.001)
- 調整後:IRR 1.04(95% CI 0.90–1.12、p=0.626)→有意差なし
- 死亡率:
このサブグループでは389人(4.0%)が死亡しました。- 未調整:HR 1.39(95% CI 1.14–1.70、p=0.001)
- 調整後:HR 1.28(95% CI 1.03–1.60、p=0.026)→有意に高い死亡リスク
好酸球が高ければICSが効くかも!?
適応外患者のうち、好酸球高値(>400–500/μL)あり
増悪頻度:
- 好酸球増多 + ICS使用群では、増悪が有意に減少(RR 0.70、95% CI 0.59–0.84、p<0.001)
- 好酸球増多 + ICS非使用群では、基準群と比較しわずかに増加傾向(RR 1.17、95% CI 1.00–1.38、p=0.053)
入院頻度:
- 好酸球増多 + ICS使用群で有意に減少(RR 0.56、95% CI 0.35–0.90、p=0.016)
死亡率:
ICS使用で好酸球増多あり:HR 0.62(95% CI 0.23–2.41、p=0.619)→有意差なし
ICS非使用で好酸球増多あり:HR 1.50(95% CI 0.74–3.01、p=0.262)→有意差なし
🧠 臨床的にどう活かす?
✅ ICSは「誰でも使う薬」ではない
ICSは「喘息・ABPA・COPD合併」のある症例に限定して使用するのが原則です。
✅ 「好酸球数」が高ければメリットがあるかもしれない
ICSの「利きそうな患者」と「感染リスクだけ上がる患者」の見極めが大切です。これは好酸球で区別すべきでしょうか。
✅ 気管支拡張症のICS使用を再評価するべきタイミングかもしれません
RCTでの検証が待たれますが、血中好酸球数に基づいた個別化治療の第一歩として、本研究は重要な知見です。
ただし、好酸球が高い症例は単に喘息と診断できていなかっただけなのでは??とも考えてしまいます。
- Oriano M, Gramegna A, Amati F, et al. T2-High Endotype and Response to Biological Treatments in Patients with Bronchiectasis Biomedicines 2021;9:772. ↩︎
- Shoemark A, Shteinberg M, De Soyza A, et al. Characterization of Eosinophilic Bronchiectasis: A European Multicohort Study. Am J Respir Crit Care Med 2022;205:894–902 ↩︎