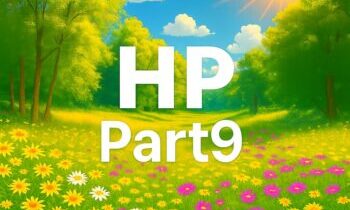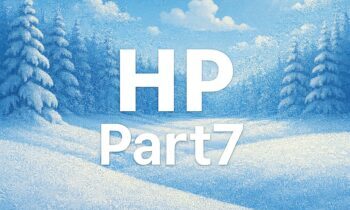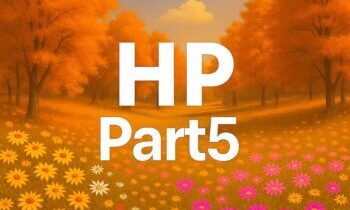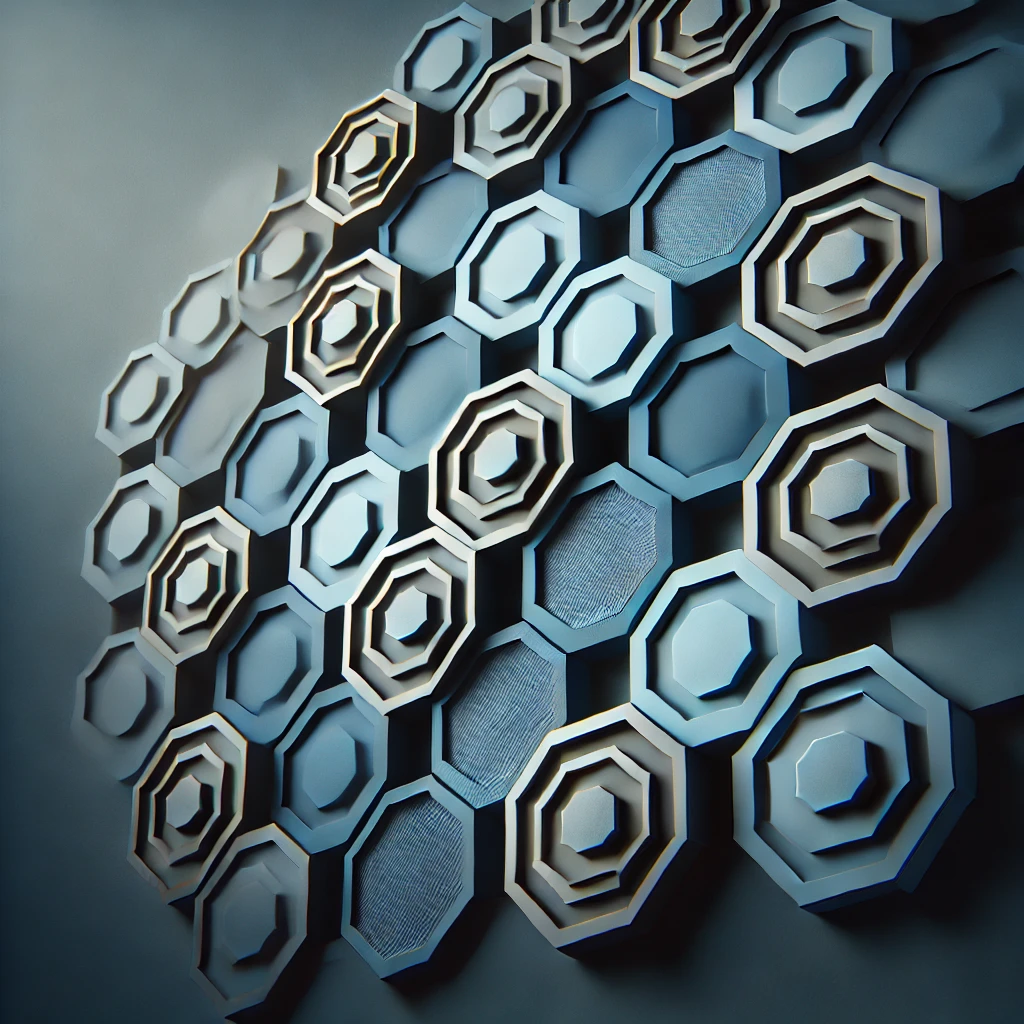 ガイドライン
ガイドライン 間質性肺疾患(ILD)の診断の流れ――膠原病ILDの注目すべき所見・症状と自己抗体とは?
膠原病に伴う間質性肺疾患 診断・治療指針2025 日本呼吸器学会・日本リウマチ学会合同 膠原病に伴う間質性肺疾患 診断・治療指針2025 作成委員会引用文献今回は、間質性肺疾患(ILD)に遭遇した際の診断アプローチについて、特に膠原病に焦点を当てて解説します。以下、まずは、過去の記事の復習になります。※詳細は、過去の記事「間質性肺疾患(ILD)の診断の流れ」参照まず最初に確認すべきこと!🔴 患者さ...