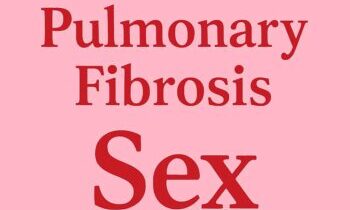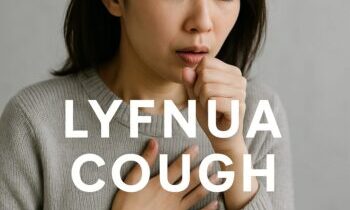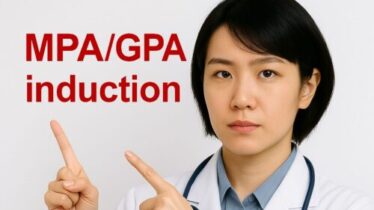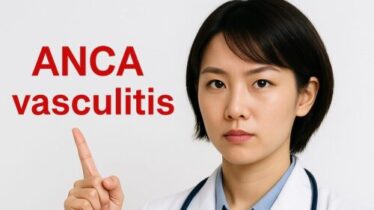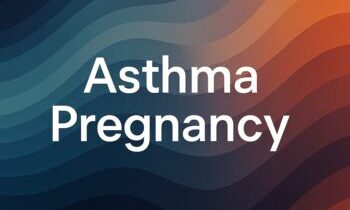 その他
その他 妊娠中の喘息治療薬は本当に安全か?〜ICSとLABAの使用と胎児への影響を検証した大規模研究〜
The Association Between Use of Inhaled Corticosteroids and Long‐Acting Beta2‐Agonists During Pregnancy and Adverse Fetal Outcomes. Wu YC, et al.Respirology. 2025.This is an open access article under t...