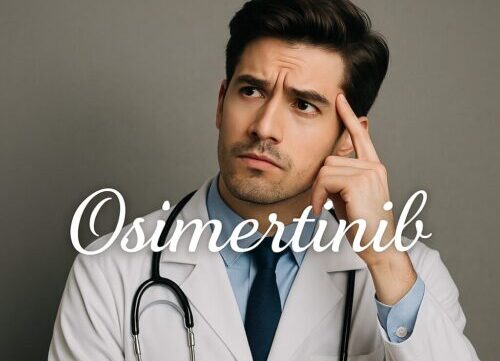Overall Survival in EGFR-mutant Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Treated with First-line Osimertinib: A Cohort Study Integrating Clinical and Biomarker Data in the United States. Joshua K. Sabari, et al. Journal of Thoracic Oncology 2025.
はじめに

非小細胞肺がん(NSCLC)の中でも、EGFR遺伝子変異を持つタイプは、日本を含むアジア人や女性・非喫煙者に多いことが知られていますね。
このEGFR変異に対して、「分子標的治療薬」として登場したのがオシメルチニブ(タグリッソ®)。
とくに脳転移にも効く第3世代TKIとして、2018年以降、一次治療のスタンダードになってきました。

しかし、臨床試験で示された生存期間(たとえばFLAURA試験の38.6か月)と、実際の診療で得られる「実臨床データ(real-world data)」との間には差があることが問題になっています。
この研究では、実際にオシメルチニブを使用した患者の「リアルな」生存データを大規模に解析し、どのような患者背景が予後に影響するのかを明らかにしようとしています。
背景
EGFR変異を有する非小細胞肺癌(NSCLC)の患者は死亡率が高い。
第3世代のチロシンキナーゼ阻害剤(TKI)であるオシメルチニブは、EGFR変異NSCLCに対する一次治療として承認されている。
本研究では、米国の医療腫瘍データベースを用いて、一次治療としてオシメルチニブを受けた進行EGFR変異NSCLC患者における実臨床の全生存期間(real-world overall survival, rwOS)および予後リスク因子グループを評価した。
方法
この後ろ向き新規使用者コホート研究は、ConcertAI、Flatiron Clinical-Genomics、COTAの各データベースから得た電子医療記録を用いた。
2018年4月1日から2022年10月30日の間にオシメルチニブ単剤による一次治療を開始した進行/転移性EGFR変異NSCLC患者を対象とした。
追跡は死亡または2023年10月31日まで行われた。
rwOSはKaplan-Meier法で推定し、多変量解析でリスク因子を評価した。
結果
1323例が解析対象で、中央値20か月の追跡期間があった。
中央値年齢は70歳(35–89歳)。
rwOS中央値は28.6か月(95% CI: 26.8–30.9)。
高リスク群では、ECOG PS ≥2で18.1か月、脳転移ありで24.3か月、肝転移ありで19.3か月、TP53共変異ありで25.7か月であった。
95%の患者が1つ以上の高リスク因子を有していた。
ECOG ≥2の割合は17%、脳転移36%、肝転移15%、TP53共変異63%。
高リスク因子を有する患者は死亡リスクが有意に高かった(すべてp≤0.011)。
2年生存率は58%、5年生存率は18%、33%の患者は二次治療を受けなかった。
結語
TKI治療の進歩にもかかわらず、進行EGFR変異NSCLC患者の長期生存率は依然として低い。
ほとんどの患者が死亡リスク因子を有しており、3分の1は二次治療に至らなかった。

感想です。
🧨リスク因子があるとどうなる?
以下の因子があると死亡リスクが有意に増加していました:
| リスク因子 | 中央rwOS | 死亡リスク(aHR) |
|---|---|---|
| ECOG PS ≥2 | 18.1か月 | 1.78 |
| 肝転移あり | 19.3か月 | 1.91 |
| TP53共変異あり | 25.7か月 | 1.30 |
| L858R変異 | 24.9か月 | 1.43 |
| 65歳以上 | 27.0か月 | 1.26 |
つまり、95%の患者が1つ以上のリスク因子を持っていたということは、
私たちが日々診ている患者さんの多くがこの「リスク群」に当てはまる可能性が高いということですね。
🤔この研究からわかること
✅ オシメルチニブでも限界がある
治験(FLAURA)での「38.6か月生存」と比べ、実臨床では「28.6か月」。
約10か月短縮している背景には、高齢・PS不良・転移の多さ・遺伝子変異の違いなどがあります。
✅ 二次治療までたどり着けない患者が多い
実に3人に1人は、一次治療だけで治療が終わっていた。
この数字は、初回治療で「どれだけ効果を出せるか」が生存に直結することを示しています。
✅ L858R変異やTP53共変異は要注意!
Exon 19 delよりもL858R変異の方が予後が悪いことが再確認されましたね。
また、TP53変異は治療抵抗性のマーカーとして、今後の治療選択の参考になります。
🧭臨床現場でどう活かす?
例えばこんなシーンで役立ちます:
- ECOG PSが2以上の患者さんに標準治療を適用すべきか? → 予後不良であることを事前に認識し、家族とも慎重に相談を
- L858R変異+肝転移+TP53陽性のようなリスクが重なる症例 → 積極的に臨床試験や新規治療オプションを検討
- 治療開始時点で予後を予測したい → この論文のリスク因子が指標になります
📝まとめ:この研究が教えてくれたこと
- EGFR変異NSCLCでも、現実の生存期間は決して長くない
- 特定のリスク因子(ECOG PS、肝・脳転移、TP53、L858R)が予後に大きく影響
- 早期から効果的な治療を選ぶことが重要
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。