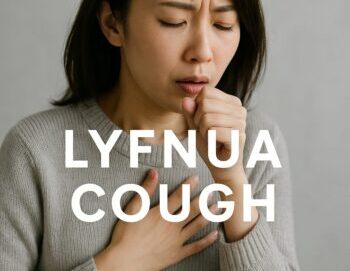近畿大学の松本先生の論文ですね。共著には、新実先生(名古屋市立大)をはじめ、日本の咳診療の第一線で活躍する先生方がずらりと並びます。
リフヌアは、味覚障害が心配で、実際の臨床では使いどころに迷う薬でしたよね。もっと使ってみようかな。
Matsumoto H, et al. Real-world usage and response to gefapixant in refractory chronic cough. ERJ Open Research 2025.
はじめに

皆さん、「慢性咳嗽」って聞くとどんな患者さんを思い浮かべますか?
8週間以上も咳が止まらない方って、本当に苦しんでいますよね。
日本では、
- 咳喘息
- 胃食道逆流症(GERD)
- 上気道咳症候群(UACS)
- アトピー咳嗽
などが主な原因です。でも、それらの治療をやっても咳が良くならないケースが約1〜4割もあるのです。これが「難治性慢性咳嗽(RCC)」です。

ここで注目されているのが「咳過敏症候群(cough hypersensitivity syndrome)」という概念です。「少しの刺激でむせる」「喉がピリピリする」といった症状を含む状態ですね。
そして今回の主役、「ゲファピサント(商品名:リフヌア Lyfnua)」は、咳を引き起こす感覚神経の過敏性を抑える新しいタイプの薬(P2X3受容体拮抗薬)です。
これまでの臨床試験では有効性が示されていましたが、実際の診療現場でどう使われているのか、どう効いているのかはよく分かっていませんでした。
この研究はそこを調べようとしたんすね。
背景
難治性慢性咳嗽(RCC)に対する新しい抗咳薬であるP2X3拮抗薬ゲファピサントの実臨床における有効性は、いまだ十分に理解されていない。
本研究は、RCC患者に対するゲファピサントの実臨床使用とその効果を評価することを目的とした。
方法
本多施設後ろ向き研究では、咳嗽クリニックを受診し、ゲファピサントを処方されたRCC患者を対象とした。
収集データには、基礎的な人口統計情報、咳嗽の特徴、ゲファピサントの効果、味覚障害の程度(いずれも咳嗽専門医が評価)、および中止後の咳嗽の経過が含まれた。
結果
272例が解析対象となった。
対象は主に中年女性で、ほとんどが喘息性咳嗽を併存し、乾性咳嗽かつ日中優位の咳嗽を呈していた。
患者の半数は0~10スケールで5以上の反応(改善)を示し、そのうち25%は8以上の反応(改善)を報告した。
反応(改善)が得られた患者(レスポンダー)の多くは、2週間以内に改善を認めた。
治療期間の中央値は32日(四分位範囲14–175日)であり、レスポンダーではより長期間使用されていた。
レスポンダーは、
- 治療前の咳嗽が重度であったこと、
- 乾性咳嗽、
- 喘息性咳嗽の併存、および
- 特有の喉頭感覚
を有していた傾向があった。
中止後もレスポンダーには咳嗽の持続的な改善が見られた。
味覚障害の有無はゲファピサントの効果とは関連せず、煙、乾燥空気、香りなどの咳嗽誘因がある患者では味覚障害が少なかった。
結語
ゲファピサントは、本多施設の実臨床において、迅速かつ有効な抗咳効果を示した。

勉強したいと思います!!
どんな結果だったか?
🔸 対象となった人たち
- 平均年齢:56歳くらい
- 女性が約65%
- 咳の平均継続期間:3年超え(つらい…)
- 多くが「咳喘息」などの喘息系の病態を合併
🔸 ゲファピサントの効果
- スコア0〜10点中、半分の人が5点以上の効果あり!
- 特に25%の人が「8点以上」と強く効いた(スーパーレスポンダー)
- 効果があった人の約7割が2週間以内に改善
▶️ 早く効くことが多いのが特徴!
🔸 どんな特徴の人に効きやすい?
- 治療前の咳が重症だった人
- 乾いた咳が多い人
- 咳喘息などの喘息タイプの人
- 喉に「イガイガ」「チクチク」「分泌感」などの違和感がある人
▶️ 特にこの④の「喉の感覚」がゲファピサントが効くサインかも!
🔸 副作用:味覚障害
- 約25%の人が味覚に違和感(無味・金属っぽい味など)
- ただし、咳のトリガー(煙や乾燥空気、香りなど)がある人では味覚障害が少なかったのは興味深いですね。
この研究から何が読み取れる?
この研究から分かったのは以下のポイントです:
🟩 ゲファピサントは実臨床でもしっかり効く
→ 約半数が有効、さらに1/4は強く反応。しかも効果発現は早い!
🟩 “喉の違和感”があればチャンス!
→ 「イガイガ」「チクチク」「痰が溜まる感じ」などの感覚があると、よく効く可能性が高いです。
🟩 副作用(味覚障害)は、効き目と無関係
→ 効果があっても味覚障害を感じる人もいるし、逆もあります。味覚障害が出にくいタイプもわかりつつあります。
限界と注意点
- 評価方法は医師の主観(0~10点)で、客観性に欠ける → 医師の主観というのが少し気になるところ。
- 咳嗽の詳細な評価ツール(咳回数測定など)は使っていない
- 喉頭感覚の記録方法にばらつきあり(施設ごとに違う)
- 治療継続期間が短い人も多く、「長期効果」は未確認
実臨床にどう活かす?
🩺 問診で“喉の違和感”があるかをしっかり聞く!
→ 「イガイガしますか?」「痰は絡みますか?」「喉がむずむずしますか?」
🩺 初回投与後2週間で効果判定を
→ 多くは2週間以内に反応が出るので、早めに見極めて次の手を考えましょう。
🩺 味覚障害のリスク説明時には「乾燥空気や匂いで咳が出る人は副作用が少ないかも」と補足を
→ 「味が分からなくなるのが怖い」と不安な患者さんの説得材料になります。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。