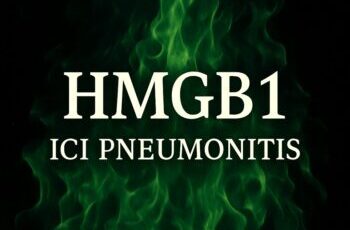広島大学の呼吸器内科を中心とした、日本国内14施設による多施設共同前向き研究ですね。
Kakuhiro Yamaguchi et al. The clinical potential of HMGB1 for the risk assessment of severe checkpoint inhibitor pneumonitis: A prospective multicenter study (CS-Lung004). European Journal of Cancer 2025
はじめに

免疫チェックポイント阻害薬(ICI)は、進行がんに対する治療効果を大きく向上させた素晴らしい薬剤ですね。しかしその一方で、命に関わるような免疫関連有害事象(irAE)も引き起こす可能性があるため、我々臨床医にとっては慎重な対応が求められます。
特に肺障害(checkpoint inhibitor pneumonitis:CIP)は、ICIに関連する最も致死的な副作用の一つであり、早期発症や重症例(Grade 3以上)は、明らかに予後を悪化させることが知られています。

ただ、これまで重症CIPを予測するバイオマーカーは確立されておらず、「誰が危ないのか」を見分ける方法がなかったのですね。
そこで本研究では、細胞傷害や炎症のマーカーとして知られるHMGB1(High Mobility Group Box 1)に着目し、重症CIPの発症リスクを血液で予測できるかどうかを前向き・多施設共同で検証しました。
HMGB1とは何か?
核内タンパク質の一種で、正常な細胞内ではDNAの構造を整えたり、転写因子の働きを助けたりする「補助的な役割」を果たしています。
しかし――
細胞がダメージを受けたり、壊死すると、HMGB1は細胞外に漏れ出します。
この「漏れたHMGB1」は、もはや無害な存在ではなくなります。
HMGB1の病態生理学的な役割
細胞外に放出されたHMGB1は、“DAMPs(Damage Associated Molecular Patterns)”の一つとして機能し、以下のような作用を引き起こします:
- 免疫細胞(マクロファージや樹状細胞)を活性化
- 炎症性サイトカイン(IL-6やTNF-αなど)を誘導
- 受容体(RAGEやTLR2/4)を介して、炎症反応を促進
なぜHMGB1は肺障害と関係するのか?
肺の上皮細胞(特にI型肺胞上皮)は、HMGB1の受容体であるRAGE(Receptor for Advanced Glycation End products)を高発現しているため、HMGB1の影響を非常に受けやすい臓器です。
そのため、以下のような病態でHMGB1上昇→肺炎や線維化を助長することが報告されています:
- 放射線肺炎
- 急性増悪を伴う間質性肺炎
- 免疫チェックポイント阻害剤関連肺障害(CIP)
- ARDS(急性呼吸窮迫症候群)
それでは本題に入ります。
背景
免疫チェックポイント阻害剤関連肺障害(CIP)、特にグレード3〜5で投与6〜12週間以内に発症するものは、がん患者の予後を悪化させる。
しかし、CIPのリスク評価法は確立されていない。
本研究は、重症CIPのリスク評価に有用な血中バイオマーカーの同定を目的とした前向き研究である。
方法
この多施設前向き研究では、初回治療として抗PD-1/PD-L1抗体を受けた非小細胞肺がん(NSCLC)患者を対象にした。
HMGB1(high mobility group box 1)を指標として、抗PD-1/PD-L1抗体投与後3ヶ月以内に発症したグレード3〜5のCIP(CIPG3–5/3months)のリスク評価能力を検討した。
評価は探索コホート(2021年12月〜2022年11月)と検証コホート(2022年12月〜2023年11月)で行った。
結果
CIPG3–5/3monthsの発症率は探索コホートで8.2%、検証コホートで6.2%であった。
探索コホートにおけるROC解析では、HMGB1のカットオフ値を8.1 ng/mLと設定し、AUCは0.732。
検証コホートでは感度80.0%、特異度71.1%を示した。
高HMGB1群は、そうでない群に比べCIPG3–5/3monthsの発症率が有意に高かった。
さらに、HMGB1は他の免疫関連有害事象(irAE)では上昇しておらず、CIP特異的なマーカーである可能性が示唆された。
結語
HMGB1は重症CIPのリスクを特異的に評価できる血清バイオマーカーである。

勉強したいと思います!!
どんな結果だったか?
対象患者とコホートの概要
- 対象:非小細胞肺がん(NSCLC)の患者 142名
- 免疫療法:抗PD-1(例:ニボルマブ、ペムブロリズマブ)または抗PD-L1(例:アテゾリズマブ、デュルバルマブ)
- コホート分け:
- 探索コホート:61名(2021年12月~2022年11月)
- 検証コホート:81名(2022年12月~2023年11月)
どれくらいCIPが起きた?
| CIPの分類 | 探索コホート | 検証コホート | 全体 |
|---|---|---|---|
| Grade 3–5(重症)CIP(3か月以内) | 8.2% (5/61) | 6.2% (5/81) | 7.0% (10/142) |
| Grade 1–5(全例)CIP(3か月以内) | 9.8% | 14.8% | 12.7% |
| Grade 1–5(全例)CIP(1年以内) | 19.7% | 27.2% | — |
▶ 重症CIPは3か月以内に発症することが多く、約7%の頻度
HMGB1(バイオマーカー)とCIPの関連
HMGB1のベースライン値(治療前の血中濃度)
- 全体の中央値:5.7 ng/mL
- 重症CIPを発症した人のHMGB1値は、非発症群よりも有意に高値
ROC解析(CIP発症を予測するカットオフの精度)
- カットオフ値:8.1 ng/mL
- この値を境にして、CIP発症リスクを大きく分けることができた。
感度・特異度(検証コホート)
- 感度(CIPが起きた人を陽性と判定できる割合):80.0%
- 特異度(CIPが起きない人を陰性と判定できる割合):71.1%
- ROC曲線のAUC(精度の指標):0.732 そこそこの判別性能
HMGB1の値でリスクがどう変わったか?
| コホート | HMGB1 ≥ 8.1 ng/mL | HMGB1 < 8.1 ng/mL | P値 |
|---|---|---|---|
| 探索 | 18.2% 発症 | 2.6% 発症 | 0.028 |
| 検証 | 15.4% 発症 | 1.8% 発症 | 0.035 |
| 全体 | 16.7% 発症 | 2.1% 発症 | < 0.01 |
→ HMGB1が高い患者では、重症CIPの発症率が約8倍!
この研究から何が読み取れる?
🔹 重症CIPは3か月以内に起きやすい(全体の7%)
🔹 治療前のHMGB1が8.1 ng/mL以上なら、重症CIPの発症リスクは約8倍
🔹 HMGB1は他のirAEでは上昇しない → CIPに特異的?
🔹 診断前にリスクを「予見」できる可能性があるかも
限界と注意点
- サンプルサイズが少ない(n=142)ため、今後はより大規模な外部コホートでの再検証が必要ですね。
- 他のirAE(例:内分泌障害など)の系統的評価は不十分であり、「CIPに特異的」と断言するにはやや慎重さも必要です。
実臨床にどう活かす?
この研究は、我々が日常診療で最も警戒すべき免疫関連有害事象(irAE)のひとつである重症CIP(免疫チェックポイント阻害剤関連肺障害)を、治療開始前に予測できる可能性を示した非常に意義深いものです。
たとえば、初診時の血液検査でHMGB1が高値であれば、抗PD-1抗体の使用を再考し、抗PD-L1抗体への切り替えや抗CTLA-4抗体との併用を避けるといった治療戦略の立案に活用できるかもしれません。
また、肺機能に余力のない患者さん(例:高齢者やCOPD合併例)でHMGB1が高値の場合には、ICIの使用自体を慎重に検討するという選択肢も現実的になるでしょう。
さらに、HMGB1高値の患者には、定期的な胸部CTの撮像やSpO₂のチェック頻度を増やすなど、モニタリングを強化することが、CIPの早期発見と迅速な対応につながると考えられます。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。