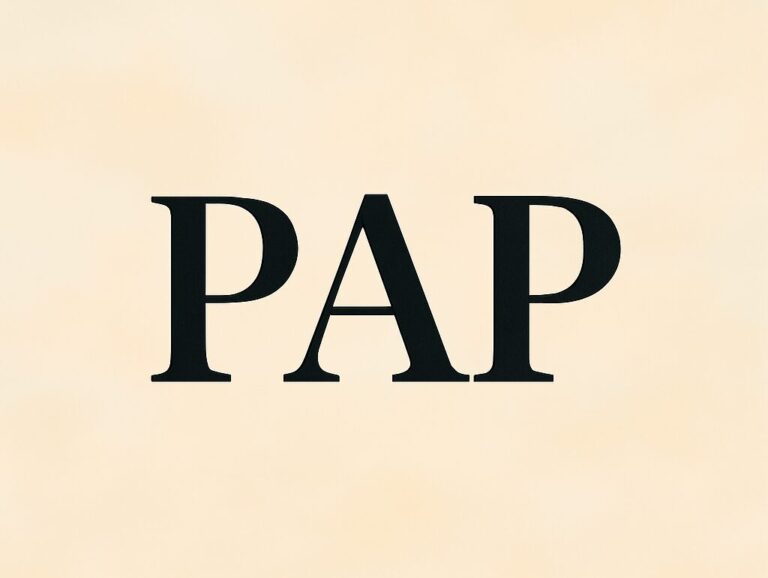自己免疫性肺胞蛋白症(aPAP)は、抗GM-CSF抗体によりGM-CSFの働きが抑制され、肺内でのGM-CSF不足によって発症する稀な疾患です。
そのため、GM-CSFを吸入薬として外から補う治療が有効ではないかと考えられてきました。
近年では、サルグラモスチム製剤「サルグマリン®」が2024年に本邦で保険適応となり、実臨床でも使用が開始されています。
本稿では、もう一つのGM-CSF製剤であるモルグラモスチムの有効性と安全性を評価した第3相RCT(NEJM)を解説します。
Phase 3 Trial of Inhaled Molgramostim in Autoimmune Pulmonary Alveolar Proteinosis. Trapnell BC, et al. N Engl J Med. 2025.
はじめに

aPAPは、抗GM-CSF抗体によって肺胞マクロファージの分化・機能が障害されることを原因とする、希少かつ進行性の呼吸器疾患です。
サーファクタントの代謝が阻害されることで、肺胞内にサーファクタントが過剰に蓄積し、換気血流比の不均衡や低酸素血症をきたすことが知られています。

従来の標準治療は、蓄積したサーファクタントを物理的に洗い流す「全肺洗浄(WLL)」でしたが、病因そのものにはアプローチできません。そこで注目されたのが、GM-CSFの補充療法です。
GM-CSF製剤には以下の2種類があります:
- サルグラモスチム(糖鎖修飾あり)
- モルグラモスチム(非糖鎖型で安定性に優れる)
本研究で取り上げられているモルグラモスチムは、吸入用の組換えヒトGM-CSF製剤であり、病態の根本に作用する可能性がある治療選択肢です。
過去にも小規模な試験はありましたが、今回は国際多施設の第3相RCTとして、164例を対象に48週間の吸入治療を実施し、有効性と安全性が評価されています。
背景
自己免疫性肺胞蛋白症(aPAP)は、GM-CSFに対する自己抗体によって肺胞マクロファージの機能が障害され、肺胞内にサーファクタントが蓄積して低酸素血症を引き起こす疾患である。
モルグラモスチムは吸入可能な組換えヒトGM-CSFであり、本疾患に対するその有効性と安全性を検討する必要がある。
方法
本試験は第3相、二重盲検、プラセボ対照、無作為化臨床試験である。
対象はaPAP患者で、1日1回吸入にてモルグラモスチム300μgまたはプラセボを48週間投与した。
主要評価項目は、ベースラインから24週後までのヘモグロビン補正DLCO(予測値%)の変化である。
副次評価項目は、
- 48週までのDLCO変化、
- St. George’s Respiratory Questionnaireの総合(SGRQ-T)
- 活動(SGRQ-A)スコア、
- 運動耐容能の24週および48週時点
での変化とした。
結果
164例が無作為化され、モルグラモスチム群は81例、プラセボ群は83例であった。
24週時点のDLCOの最小二乗平均変化は、
- モルグラモスチム群で+9.8%ポイント(95%CI 7.3~12.3)、
- プラセボ群で+3.8%ポイント(95%CI 1.4~6.3)、
- 群間差は+6.0%ポイント(95%CI 2.5~9.4、P<0.001)
であった。
48週では、それぞれ+11.6%ポイント、+4.7%ポイントであり(P<0.001)、差は持続していた。
SGRQ-Tは、モルグラモスチム群で−11.5点、プラセボ群で−4.9点の改善を示し(P=0.007)、
一方でSGRQ-Aは24週時点で有意差がなく、
それ以降の副次評価項目についての統計学的推論は行われなかった。
有害事象および重篤な有害事象の発生率は、両群間で同程度であった。
結語
吸入モルグラモスチムは、aPAP患者においてプラセボと比較してDLCOをより改善した。

勉強してみます。
どういう結果だったの?
主要評価項目:DLCOの変化(ヘモグロビン補正)
- 24週後の変化
モルグラモスチム群:+9.8%ポイント
プラセボ群:+3.8%ポイント
群間差:+6.0%ポイント(P<0.001) - 48週後の変化
モルグラモスチム群:+11.6%ポイント
プラセボ群:+4.7%ポイント(P<0.001)
DLCOはサーファクタントの蓄積程度やガス交換機能を反映するので、この改善は意味が大きいですね。
副次評価項目:QOL(St. George’s Respiratory Questionnaire)
- SGRQ-T(総合スコア)24週時点
モルグラモスチム群:−11.5点
プラセボ群:−4.9点
→ 有意な改善(P = 0.007) - SGRQ-A(活動スコア)24週時点
有意差なし → これにより、階層化解析により以後の評価は有意性を検定せず
運動耐容能(MET)
- 24週:差 0.4MET(95%CI −0.1~0.9)
- 48週:差 0.6MET(0.1~1.0)
※ただし形式上の統計的推論は実施されていない。
安全性
- 有害事象の発生率は両群でほぼ同等(約85%)
- 重篤な有害事象:モルグラモスチム群17%、プラセボ群24%
- 中止例はわずか
- COVID-19や下痢の発現がモルグラモスチム群でやや多め(22%、11%)
サルグラモスチム vs モルグラモスチム:何が違う?
吸入GM-CSF療法には、現在2つの主要製剤があります:
- サルグラモスチム
- モルグラモスチム
いずれも、抗GM-CSF抗体による機能障害に対し、外因性GM-CSFを補うことで肺胞マクロファージの機能を回復させるという同じ治療戦略に基づいていますが、製剤特性と臨床試験デザイン・結果に違いがあります。
製剤としての主な違い
| 項目 | サルグラモスチム | モルグラモスチム |
|---|---|---|
| 製造由来 | 酵母由来(糖鎖あり) | 大腸菌由来(非糖鎖型) |
| アミノ酸配列 | ヒト型と一部異なる | ヒトGM-CSFと完全一致 |
| 安定性・純度 | 中程度 | 高い(吸入製剤として有利) |
| 日本での承認状況 | 承認・保険適用済(2024年〜) | 未承認(2025年10月時点) |
臨床試験デザインと結果の違い
| 項目 | サルグラモスチム | モルグラモスチム |
|---|---|---|
| 代表的試験 | IMPALA試験(2019) | NEJM第3相試験(本論文, 2025) |
| 主要評価項目 | A–aDO₂ | DLCO(%予測値) |
| QOL評価(SGRQ) | 改善傾向、統計的有意差なし | SGRQ-Tで有意改善(−6.6点, P=0.007) |
| DLCOの有意差 | 群間差小、明確な有意差は示せず | 24週 +6.0%pt(P<0.001) |
| 治療期間 | 24週 | 48週 |
| 副次評価項目 | CT・WLL頻度など | A–aDO₂・WLL頻度など(探索的に有利傾向) |
ポイント
- モルグラモスチムはより実臨床的な指標(DLCO、QOL)で有意差を示し、48週の長期安全性データも報告されています。
- サルグラモスチムはすでに保険適用があり、現時点で唯一使用可能な製剤です。
- 両剤を直接比較した試験はなく、現時点で明確な優劣を論じることはできませんが、結果だけみるとモルグラの方が有望そうな印象ですね。
論文の臨床的意義
この第3相RCTにより、吸入モルグラモスチムがaPAPに対する有効な病態修飾療法となり得ることが示されました。
特に、
- DLCOの有意な改善(+6.0%pt)
- QOLスコア(SGRQ-T)の有意改善(−6.6点)
- 48週にわたる効果の持続と安全性
といった点は、従来のWLL中心の治療から吸入療法へのシフトを後押しするものです。
現在、日本ではサルグラモスチム製剤(サルグマリン®)が使用可能ですが、今回の結果は、モルグラモスチムの保険収載・承認に向けた重要な一歩となる可能性があります。
今後、予後やWLL回避率、反応予測因子(抗体価や画像所見など)に基づく個別化治療の確立が課題となりますが、本研究は、aPAP治療の選択肢を広げる臨床的に価値ある成果であると言えるでしょう。
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。