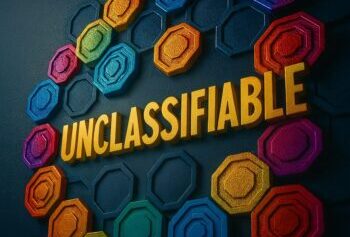Ryerson CJ et al. Update of the International Multidisciplinary Classification of the Interstitial Pneumonias: An ERS/ATS Statement. European Respiratory Journal 2025.
間質性肺疾患(ILD)の診断は、多職種合議(multidisciplinary discussion: MDD)が基本です。
しかし、全ての症例がきれいに既存の診断枠組みに当てはまるわけではありません。
検査を重ねても、臨床・画像・病理所見を総合しても「診断に至らない」症例が一定数存在します。
これが 分類不能ILD(Unclassifiable ILD) です。
2025年の国際ステートメントでは、この「分類不能ILD」が改めて注目され、明確な定義づけと研究課題が提示されました。
本稿では、2013年と2025年の定義を比較しながら、解説します。
2013年ATS/ERSステートメントにおける定義
2013年のATS/ERSステートメントでは、分類不能特発性間質性肺炎(Unclassifiable IIP) は以下のように定義されています:
- 臨床・画像・病理データが不十分
- 臨床・画像・病理所見の不一致
- 治療介入後に修飾された症例(例:治療後に典型的パターンが消失した状態でMDDした場合)
- 現行分類に含まれない新しい疾患や亜型
- 一人の患者に複数のパターンが併存する場合(複合型)
このように、2013年時点では「診断に至らないケースの受け皿」として広く設定されており、
診断確信度の数値化はなされていませんでした。
2025年ERJステートメントにおける定義
2025年の国際ワーキンググループは、より具体的で操作的な定義を提示しました:
- 分類不能ILDの定義:
包括的なMDDを経ても、特定の診断を50%以上の確信度で下せない場合。 - 診断確信度の枠組み:
- ≥90% → 確定診断(Confident diagnosis)
- 51–89% → 暫定診断(Provisional diagnosis)
- ≤50% → 分類不能ILD
複合型の位置づけ:2013 vs 2025
2013年ステートメント
- 複合型(combined patterns) は、分類不能IIPの原因のひとつとして明確に記載されていました。
- 基本的に「複合型=分類不能」と直結する扱いであり、複合パターンがあれば診断がつかず、分類不能に振り分けられるケースが多かった。
2025年ステートメント
- 複合型はまず「独立して認識すべき概念」として提示。
- 画像や病理で複数のパターンが併存している場合、まずは「複合型」として把握する。
- その上で、診断確信度の枠組みを用いて判断:
- 優位な特定パターンが存在し、その診断に対する確信度が ≥51% ある場合
→ そのパターンに基づいた疾患名を診断に用いる。- 例:UIPとBIPが併存しているが、UIPとしての診断確信度が70%ある → UIPパターンを示す疾患名(特発性ならIPF、関節リウマチが背景ならRA-ILDなど)を診断に採用できる。
- どのパターンにも十分な診断確信度(≤50%)が得られない場合
→ 複合型を理由に「分類不能ILD」と位置づけられる。- 例:UIP、NSIP、PPFEが併存し、どれを優位とすべきか判断困難 → 分類不能ILD。
- 優位な特定パターンが存在し、その診断に対する確信度が ≥51% ある場合
👉👉 このように、2025年では「複合型が即分類不能」という単純な構造ではなく、グラデーションのある診断アプローチが導入されました。
2013年と2025年の比較
| 項目 | 2013年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 定義 | – 情報不足 – 所見不一致 – 治療後変化 – 新規疾患 – 複合型 を含む受け皿的概念 | 概ね2013年の定義を受け継ぐ。 そのうえで、MDD後でも診断確信度 ≤50%の場合に分類不能 |
| 診断確信度 | 記載なし | – ≥90%:確定診断、 – 51–89%:暫定診断、 – ≤50%:分類不能 |
| 複合型の扱い | 自動的に分類不能へ | 分類不能の範疇に含まれるが、 確信度により暫定診断に分類可能 |
分類不能ILDの原因と臨床的な考え方
- 臨床・画像・病理データが不十分
- 追加の検査や情報収集によって診断確信度を高める努力が必要。
- 特に治療介入が必要な症例では積極的にデータを集めるべき。
- 一方で、軽症例や進行が遅い症例では経過観察し、時間とともに得られるデータを待つ選択肢もありうる。
- 臨床・画像・病理所見の不一致
- MDDで診断名が変わる可能性がある領域。
- 採取部位や時期の違いで所見が一致する場合もあり、再検査も選択肢となる。
- 治療介入後に修飾された症例
- 例:ステロイド治療後に典型的パターンが消失した状態でMDDを行う場合。
- やむを得ない面があるが、治療効果を考慮して診断を検討することが望ましい。
- 現行分類に含まれない新しい疾患や亜型
- 稀ではあるが、今後の知見蓄積につながる重要な症例群。
- 症例報告や多施設でのMDDによる検討が推奨される。
- 複合型(combined patterns)
- 複数の画像・病理パターンが併存する場合。
- 詳細については「複合パターン」の記事を参照。
まとめ
2013年では、分類不能ILDは「診断の限界を示す受け皿」として位置づけられていましたが、
2025年の今回は、診断確信度を基準に扱うようになり、できるだけ確信度を高めるために
- 十分なデータ収集
- 診断医の経験・スキルの向上
- 新しい検査法の開発
が重要視されるようになっています。
過去の記事はこちら
【新国際分類2025】間質性肺炎の新しい整理法 – 背景と全体像を押さえよう
【新国際分類2025】その2 間質性肺炎診断はこう進める!―実践的アプローチ解説―
【新国際分類2025】その3 Interstitital patternsとAlveolar filling patternsの全体像とパターン分類
【新国際分類2025】その4 Usual Interstitial Pneumonia(UIP)はただの画像・病理パターン―“特発性”か“二次性”かの見極めが重要
【新国際分類2025】その5 Nonspecific interstitial pneumonia(NSIP)
【新国際分類2025】その6 気管支中心性間質性肺炎(Bronchiolocentric Interstitial Pneumonia: BIP)ってな~に?
【新国際分類2025】その7 びまん性肺胞障害(Diffuse Alveolar Damage: DAD)を理解する
【新国際分類2025】その8 Pleuroparenchymal Fibroelastosis(PPFE)を学ぶ
【新国際分類2025】その9 Lymphoid interstitial pneumonia(LIP)パターンを見たら、まず“二次性”を疑え!
【新国際分類2025】その10 Organising Pneumonia(OP)を極める
【新国際分類2025】その11 Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease(RB-ILD)を理解する ―ほぼ喫煙関連?
【新国際分類2025】その12 Alveolar Macrophage Pneumonia(AMP)―DIPからAMPへ

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。