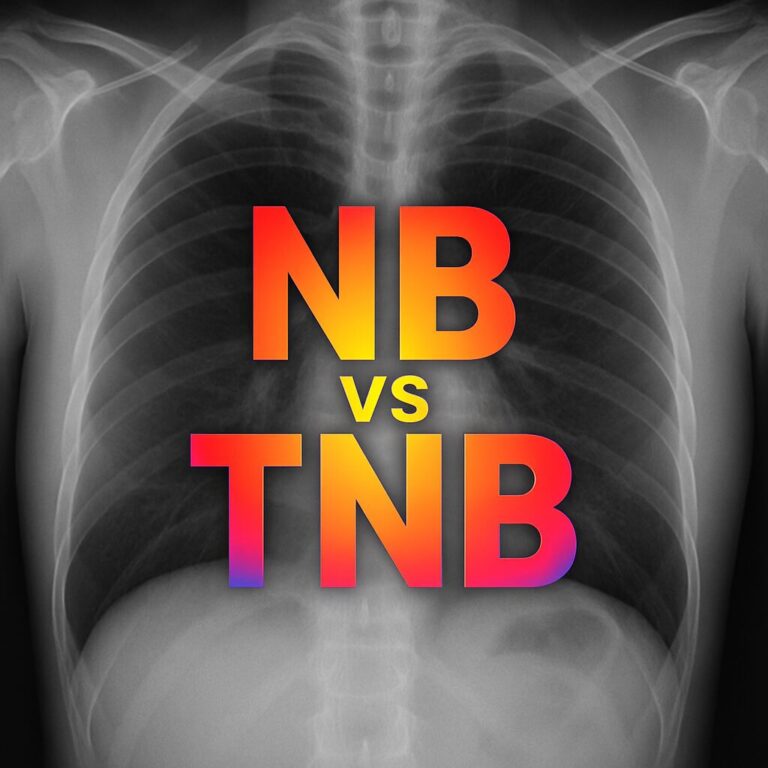新しい検査技術の論文ですね。
Navigational Bronchoscopy or Transthoracic Needle Biopsy for Lung Nodules. R.J. Lentz, et al. ew England Journal of Medicine 2025.
はじめに

みなさんも臨床で、CTで偶然見つかった小さな肺結節に遭遇することが多いのではないでしょうか?
「がんかどうか」はっきりさせるためには生検が必要ですが、実際にどの方法を選ぶべきか、悩むケースも多いですよね。
ナビゲーション気管支鏡検査(NB):CT画像を元に末梢の気道まで誘導し、生検を行う新しい技術。安全性は高いが、従来は診断精度にやや難あり。
経皮肺針生検(TTNB):CTでピンポイントに刺す高精度の手技。ただし気胸リスクが高い(〜25%)という弱点あり。

この研究は、NBが最新の3D画像技術(デジタルトモシンセシスなど)を活用することで、TTNBと同等の診断精度を持つかを、無作為化試験で初めて明らかにしようとしたものです。
背景
毎年、何百万もの肺結節が偶発的または肺がんスクリーニングによって発見され、その多くが良性か悪性かを判断するために生検が行われる。
末梢肺結節の生検には、ナビゲーション気管支鏡検査(NB)とCTガイド下経皮肺針生検(TTNB)が一般的に用いられているが、両者の診断精度の相対的な比較は明らかではなかった。
方法
本多施設無作為化非劣性試験では、直径10〜30 mmの中〜高リスク末梢肺結節を有する患者を、NBまたはTTNBのいずれかに割り付けた(米国の7施設で実施)。
主要評価項目は、12か月間の追跡で確認された正確な特定診断(がんまたは特定の良性疾患)を得られた患者の割合であった。
副次評価項目には、気胸などの手技関連合併症が含まれた。。
結果
主要解析対象の234人のうち(うち5人が追跡不能)、
- NB群では119人中94人(79.0%)、
- TTNB群では110人中81人(73.6%)
が正確な特定診断に至った(絶対差 5.4ポイント;95%信頼区間 −6.5〜17.2;非劣性に対するP値 = 0.003、優越性に対するP値 = 0.17)。
気胸はNB群で3.3%(4/121)、TTNB群では28.3%(32/113)に発生し、そのうち胸腔ドレナージや入院が必要であったのは、NB群で0.8%、TTNB群で11.5%であった。。
結語
0〜30 mmの末梢肺結節において、ナビゲーション気管支鏡検査の診断精度は経皮肺針生検に対して非劣性であった。

勉強したいと思います!!
🔍 Navigational Bronchoscopyの具体的な手技
1. 事前のCTスキャンによるプランニング
- 検査前に撮影された胸部CT画像をもとに、結節までのルート(ナビゲーションプラン)をソフトウェアで計画。
- ナビゲーションシステム(例:Illumisite Fluoroscopic Navigation Platform)が使用される。
2. 電磁ナビゲーションシステムの使用
- 電磁場(electromagnetic field)を利用して、内視鏡内のカテーテルの位置をリアルタイムで追跡。
- CTで作成された3Dマップと実際の体内位置を一致させる。
3. 気管支鏡挿入と局在確認
- 患者を麻酔下に置き、気管支鏡を挿入。
- 標的結節の位置を、ラジアル内視鏡超音波(radial EBUS)で確認。
- 必要に応じて、デジタルトモシンセシス(digital tomosynthesis)を併用し、カテーテルの方向を微調整。
4. 生検の実施
- 生検は、細胞診ブラシ、針吸引、鉗子など複数のツールで実施。
- 組織が得られたら、迅速細胞診評価で十分な検体が採取されているかその場で確認。
5. 術後の確認
- X線透視で気胸(pneumothorax)の有無を確認。
- 必要に応じて追加検査や処置を行う。
どっちが良かった?数値で比較!
| 評価項目 | NB群 | TTNB群 | コメント |
|---|---|---|---|
| 診断精度(12ヶ月以内の正確な診断) | 79.0% | 73.6% | NBは非劣性 |
| 手技時間(中央値) | 36分 | 25分 | NBの方がやや長いが、許容範囲内 |
| ROSE使用率(術中迅速細胞診) | 96% | 7% | NBではほぼ全例で活用されている |
| 気胸(全体) | 3.3% | 28.3% | TTNBでは4人に1人が気胸に! |
| 胸腔ドレナージや入院を要した気胸 | 0.8% | 11.5% | NBではごくわずか |
📝 補足:放射線被ばく量はNBの方が高かったですが、単位が異なり直接比較は困難とのこと。
🔍 サブグループ解析から見えること
▼ 各条件での診断精度の差(NB – TTNB)
| サブグループ | 差(%ポイント) | 解釈 |
|---|---|---|
| 全体 | +5.4 | NBがやや有利 |
| 外側肺区域 | +6.2 | 結節が肺の外側にあるとNBが高精度 |
| 気管支サインあり | +14.5 | CTで気管支が結節に接している場合はNBが圧勝 |
| 結節径 <15mm | +3.5 | 小さな結節でもNBが有効 |
| 癌確率 <50% | +12.9 | リスク低めの症例でもNBがしっかり診断 |
📊 これらの結果からも、NBは多くの臨床状況で信頼できる選択肢であることがわかります。
この研究から何が読み取れる?
- NBの診断精度は、TTNBと肩を並べる
- 最新のナビゲーション技術と3D画像(デジタルトモシンセシス)の導入が奏功。
- TTNBの診断率が思ったより低かった?
- 対象が小径結節(中央値15mm)だったことや、厳格な12か月追跡を行ったため。
- 診断だけでなく、安全性が違う
- これだけ気胸の発生率が違うと、目的やリスクによってはNBが選択されることが多くなるでしょうか。
限界と注意点
- NBは熟練医によって施行されており、すべての施設で同様の精度を再現できるとは限らない。
- 術者・患者は非盲検のため、手技や周辺対応に影響の可能性あり。
- 費用対効果(コスト評価)は未検討。
- 中枢結節や複数病変のあるケースには未対応。
実際の現場ではどう使う?
この結果を受けて、以下のような選択が推奨されます:
✅ 高リスク患者(高齢者、COPD、在宅酸素)ではNBを第一選択に
✅ 結節が小さい or 外側肺区域の場合もNBが有効
✅ CTで気管支サインがあればNBで積極的にアプローチ
NBの普及により、「安全かつ精度の高い生検」がより多くの患者に提供できるようになりますね。
📘 まとめ
- 最新技術を用いたNBは、TTNBと同等以上の診断精度を発揮。
- 気胸などの合併症が大幅に少なく、安全性においてはNBが圧倒的に有利。
- サブグループ解析からも、NBの適応が広いことを確認。
- 適切な症例選定と施設体制が整えば、NBは新たな標準となる可能性があり。
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。