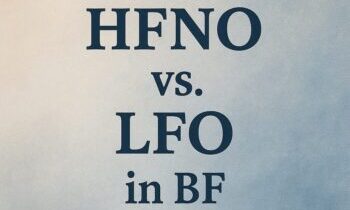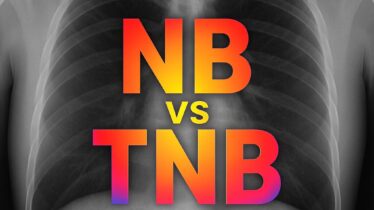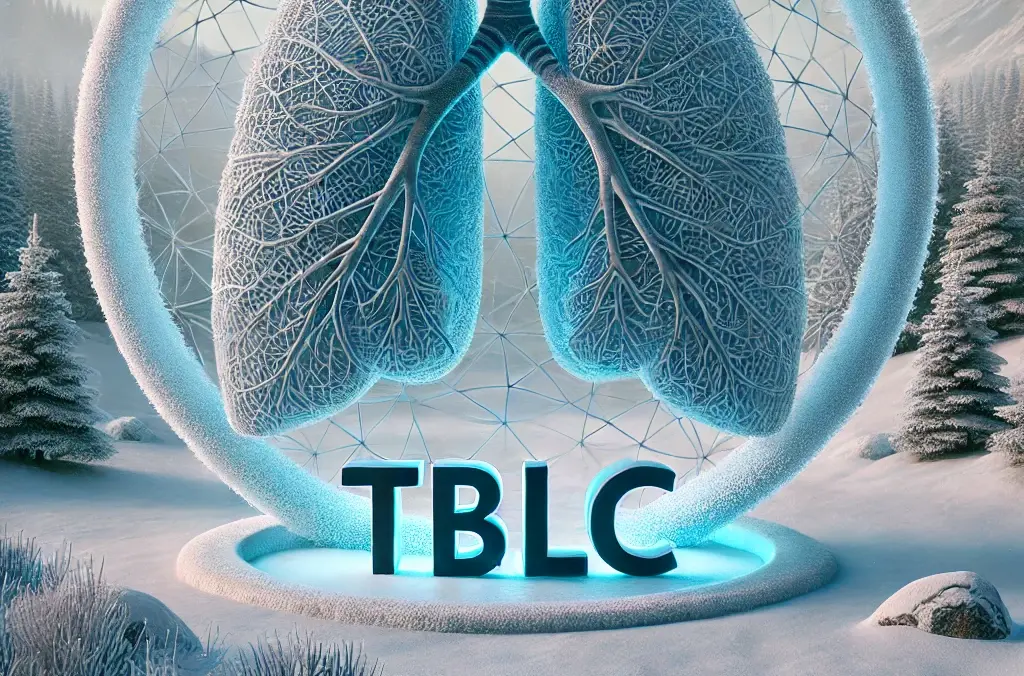論文紹介
論文紹介 肺がん診断に革新を:超音波ガイド下凍結生検(EBUS-Cryo)が切り開く中心型病変への新アプローチ
大阪公立大学からの報告ですね。Toshiyuki Nakai, et al. Application of endobronchial ultrasound-guided cryobiopsy for centrally located intrapulmonary lesions: A retrospective cohort study. Lung cancer 2025.引用文献はじめに肺が...