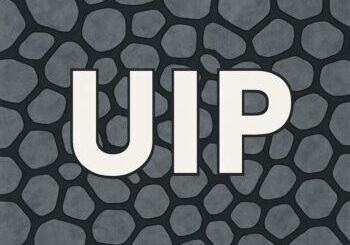過去に似たような結果は報告されていますが、この研究では、大規模かつ前向きなILDレジストリと多施設リアルワールドデータを用いて、UIPパターンの臨床的意味が基礎疾患によって異なるかを詳細に調査しているところが新規性のあるところらしいです。
Associations of interstitial lung disease subtype and CT pattern with lung function and survival. John S Kim et al. Thorax 2025.
以下上記の論文から引用します。
はじめに

間質性肺疾患(ILD)は様々な原因により発症する線維化性肺疾患の総称で、
背景疾患によって予後や治療方針が大きく異なりますね。
その中でも、IPFは最も予後が悪い疾患で、UIPパターンのHRCT所見と病理像を特徴とします。

しかしUIPパターンは、線維性過敏性肺炎(FHP)や膠原病関連ILD(CTD-ILD)にも出現することがあり、UIP=IPFとは言い切れないのが現実です。
そじて、UIPパターンは、しばしば「進行性肺線維症(PPF)」の兆候とされ、治療方針の決定にも大きな影響を与えてきました。
この研究では、大規模かつ前向きなILDレジストリと多施設リアルワールドデータを用いて、UIPパターンの臨床的意味が基礎疾患によって異なるかを詳細に調査しています。
背景
従来の研究では、放射線学的に「usual interstitial pneumonia(UIP)」パターンを示す間質性肺疾患(ILD)では予後が悪いことが示唆されている。
しかし、縦断的データとその再現性を伴う疫学的研究は不足している。
方法
Pulmonary Fibrosis Foundation Patient Registry(PFF-PR:932例)と4施設からなるILD研究のメタコホート(1579例)を用いた。
強制肺活量(FVC)の経時的変化と5年以内の移植を伴わない生存率を、
それぞれ線形混合効果モデルとCox比例ハザードモデルを用いて解析した。
副次的に、PFF-PRにおいて、放射線学的線維化の定量(データ駆動型テクスチャ解析:DTA)に基づいた解析も実施した。
年齢、性別、喫煙歴、抗線維化薬および免疫抑制薬の使用歴を調整因子とした。
結果
患者割合:
- PFF-PRでは、特発性肺線維症(IPF)が70%、線維化型過敏性肺炎(FHP)が11%、結合組織病関連ILD(CTD-ILD)が19%。
- 一方、メタコホートではIPF 21%、FHP 32%、CTD-ILD 47%だった。
PFF-PRでは、
- UIPパターンを伴うCTD-ILDはIPFよりもFVCの低下が有意に遅く(−34.4 vs −158.4 mL/年)、
- 移植を伴わない生存期間も長かった(HR 0.50, 95% CI 0.29–0.85)。
この結果はメタコホートでも再現された(FVC −53.1 vs −185.9 mL/年, p<0.0001;生存HR 0.38, 95% CI 0.27–0.53)。
FHPとIPFのFVC低下は有意差がなかった。
結語
UIPパターンを有する場合であっても、ILDのサブタイプによって肺機能の推移や予後に違いがあり、とくにCTD-ILDではIPFよりも良好な経過をたどることがある。

勉強してみます。
どういう結果だったの?
💨 FVCの年間低下量(mL/年)※PFF-PRより
| 疾患サブタイプ | UIPパターン | nonUIP |
|---|---|---|
| IPF | −158.4(−182.3~−134.6)基準 | – |
| CTD-ILD | −34.4(−122.3~−53.5)有意差あり | −43.7(−94.9~7.4)有意差あり |
| FHP | −203.4(−361.1~−45.6)有意差なし | −149.2(−214.8~−83.5)有意差なし |
上記の有意差ありなしは、IPFの年間低下量を基準とした場合に差があるかないかを示しています。
5年移植非施行生存率(HR)※PFF-PRより
| 疾患サブタイプ | HR (95% CI) | P値 |
|---|---|---|
| IPF | 1.00 (基準) | – |
| CTD-ILD(UIPパターン) | 0.50 (0.29–0.85) | 0.01 |
| FHP(UIPパターン) | 0.81 (0.39–1.70) | 0.58 |
- CTD-ILD + UIPパターン → IPFよりもFVC低下が遅く、移植を伴わない生存率も良好。
- FHP + UIPパターン → IPFと同程度のFVC低下で、明確な差はなし。
- RA-ILDに限定した解析でもCTD-ILDはIPFよりも良好な予後。
新規性
この研究の新規性は、従来「予後不良」とされてきたUIPパターンが、すべてのILDで同様の意味を持つわけではないという点を、大規模かつ独立した2つのコホートで示したことにあります。
従来、「UIP=悪い予後」という考えが一般的でしたが、CTD-ILDではUIPを呈していてもIPFほどの進行ではないという新しい知見を提示しました。
一方でFHPはやや曖昧で、UIPパターンを示してもIPFと予後が変わらない可能性もあるという、より複雑な結果になりました。これはFHPの診断が難しく、他疾患との鑑別が難しいことが影響しているのかもしれませんね。
臨床にどう活かすか?
- UIPパターンを示すCTD-ILD患者は、比較的進行が緩やかで生存率もIPFより比較的良好であるため、過度に悲観的な予後予測を避けることが重要ですね。
- 当たり前ですが、CTD-ILDでは、抗線維化薬のみならず免疫抑制薬の併用も検討の余地あり。
- 臨床試験では、「UIPあり」だけで一括にせず、疾患別に層別化して解析することが推奨される。
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。