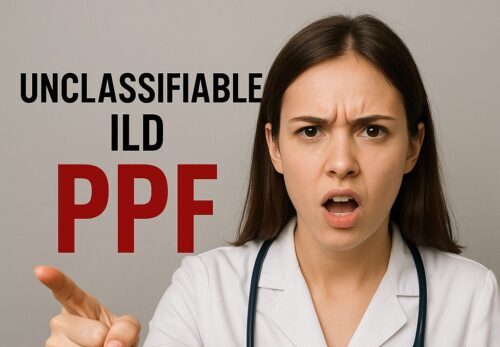聖隷浜松病院からの報告でございます。
今回は、分類不能特発性間質性肺炎(UCIIP)における進行性肺線維症(PPF)の頻度と特徴を調べた注目の研究をご紹介します。論文はこちら👇
Prevalence and clinical features of progressive pulmonary fibrosis in patients with unclassifiable idiopathic interstitial pneumonia: A post hoc analysis of prospective multicenter registry. Masato Kono, et al. Respiratory Investigation 2025.
はじめに

特発性間質性肺炎(IIP)にはいくつかのサブタイプ(IPF、NSIPなど)がありますが、中にはどうしても分類がつかないケースがあります。
それが分類不能IIP(UCIIP)です。
診断に必要な臨床所見・画像・病理のどれかが不十分だったり、互いに矛盾したりして、多職種ディスカッション(MDD)をしても診断がつかない
——これがUCIIPの正体です。

しかし「分類不能だから、進行しない」とは限りません。
中にはIPFのように進行するタイプ=進行性肺線維症(PPF)が含まれている可能性があります。
この研究では、UCIIPにおけるPPFの頻度とその臨床的特徴、予後への影響を明らかにすることを目的として、日本国内の多施設レジストリデータを用いた事後解析(post hoc)が行われました。
PPFに関する関連記事「PPFとPF-ILDって何が違うのか?わかりにくいですね。」は<こちら>
背景
特発性間質性肺炎(IIP)は、多職種による診断検討(MDD)を行っても臨床所見、画像所見、病理所見が不十分または矛盾しており、最終的な診断に至らない場合がある。
このような分類不能IIP(UCIIP)は異質性のある疾患群であり、進行性肺線維症(PPF)を呈することがある。
本研究では、UCIIP患者におけるPPFの有病率および臨床的特徴を明らかにすることを目的とした。
方法
本研究は、IIP患者222名を対象とした前向き多施設レジストリの事後解析であり、MDDにより診断されたUCIIP患者71名を対象とした。
PPFの定義は、12か月以内の症状悪化・画像進行・肺機能低下のうち2項目以上を満たすガイドライン基準、または24か月以内にPF-ILD基準(INBUILD試験)を満たすものとした。
結果
対象71例のうち、フォローアップデータが得られた66例中30例(45.5%)がPPFと診断された。
PPF群では、
- 血清サーファクタント蛋白D(SP-D)値および気管支肺胞洗浄液中の好中球比率が高く、
- %FVCと%D_LCOが低く、
- HRCTで蜂巣肺を有する割合が高く、
- 運動時の酸素脱飽和が多かった。
また、抗線維化療法や在宅酸素療法の使用率、急性増悪の発生率、予後不良がPPF非該当群に比べて有意に高かった。
Cox比例ハザード解析では、PPFは予後不良の独立した危険因子であった。
結語
UCIIP患者においてPPFは一般的であり、予後不良と関連していた。
UCIIPにおけるPPFの適切な評価と管理が重要である。

勉強したいと思います!!
🧠 PPFを見逃すな!
PPFという概念は、IPF以外の線維化疾患でも同様の進行を呈する症例があることから生まれました。
この研究が教えてくれるのは、
「分類不能だから経過観察でいい」とは限らない。
ということです。
実際、観察期間中にPPFと診断されたUCIIP患者の死亡リスクは5.3倍(HR: 5.32)。
これ、見過ごせません。
🆕 この研究の新規性
- MDDで診断されたUCIIPに絞ってPPFを評価
- INBUILD基準と2022年ガイドライン両方を用いて解析
- SP-DやBALF好中球比率などバイオマーカーの関連も評価
これは従来のUCIIPに関する研究よりも一歩踏み込んだ内容です。
一般臨床における「分類不能ILD」として扱われる症例の中には、そもそもMDDが未実施であるために診断確定に至っていない、いわば“診断プロセスの不完全さ”による分類不能も少なくありません。
しかし、本研究の意義の一つは、全例が経験豊富な呼吸器内科医・放射線科医・病理医によるMDDを経た上でUCIIPと診断された症例に限定して解析がなされている点にあります。
つまり、「必要な検討を尽くした上でなお診断不能」である、“真のUCIIP”におけるPPFの特徴を示しているという点で、他のレトロスペクティブ研究やリアルワールドの“未分類ILD”群とは明確に一線を画す内容です。
⚠ 改善点と注意事項
- SLBの実施率が低い(20%未満) → 病理の裏付けに欠ける。
- 選択バイアスの可能性 → 急性例が少なく、長期フォローができなかった例も。
- 治療方針が主治医判断 → 統一された治療評価ではない。
本研究の結果から、UCIIPにおいてもPPFかどうかを早期に見極め、進行リスクが高い症例に対しては治療の開始時期や強度を的確に調整するという戦略が、今後ますます重要になると考えられます。
しかし一方で、UCIIPはIPFともNSIPとも最終診断が確定できない症例群であるため、治療方針を一律に定めることは困難です。
実臨床では、抗線維化薬を主軸に据えるべきか、それともステロイドや免疫抑制薬を積極的に併用・強化すべきか、その判断に迷う場面が少なくありません。
したがって、どのような病態でどの治療戦略を選択すべきかを導く明確な指針の整備が、今後の大きな課題と言えるでしょう。
🩺 臨床へのインパクト
この研究は私たちにこう問いかけています:
「分類不能」と言われた患者、ちゃんとPPFを疑っていますか?
例えば、こんな患者さん👇
- FVCが数%下がってきた
- HRCTでわずかに蜂巣肺が見える
- 6分間歩行でSpO₂が下がる
- SP-Dがじわじわ上昇中…
このようなサインがみられた場合には、PPFの存在を強く疑い、初回治療としてステロイド・免疫抑制薬と抗線維化薬のいずれを優先すべきか、その適応を慎重に検討することが重要です。
すでにステロイドや免疫抑制薬を導入している症例では、病勢や進行所見を踏まえ、抗線維化薬の上乗せ(add-on)を積極的に考慮すべき状況とも言えるでしょう。
✍ まとめ
✅ 分類不能IIPの約半数がPPF
✅ PPFは予後不良・AEリスク↑・酸素療法↑
✅ SP-D、HRCT所見、SpO2低下傾向などで早期察知を
✅ 「分類不能でもPPFは潜んでいる」ことを忘れずに!
PPFに関する関連記事「PPFとPF-ILDって何が違うのか?わかりにくいですね。」は<こちら>
<スマートフォンをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。
また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。
<PCをご利用の皆さまへ>
他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。