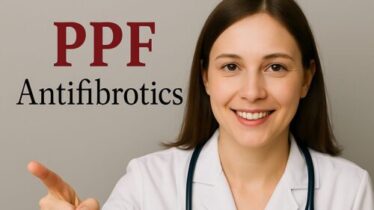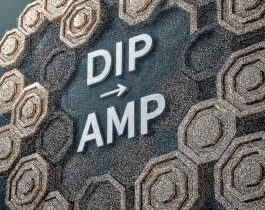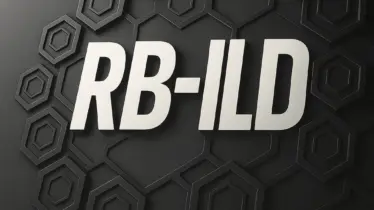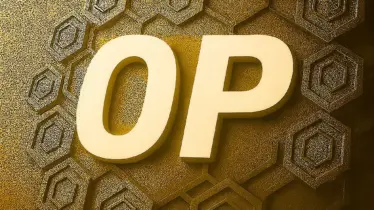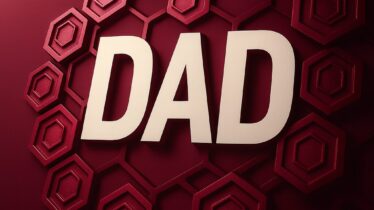感染症
感染症 HIV以外の免疫抑制によるニューモシスティス肺炎におけるステロイド──28日死亡率に差はなし、それでも見逃せない90日後の効果
抄録だけを見ると『なんだ、28日死亡率に差がないんかい!!』と思ってしまいがちですが、実際にはステロイド併用群の方が28日死亡率に改善傾向があり、さらに90日死亡率や挿管回避率では有意に良好な結果が得られています。Adjunctive corticosteroids in non-AIDS patients with severe Pneumocystis jirovecii pneumonia ...